1. 「動かさないと固まるよ」は本当?
四十肩・五十肩で肩が動かなくなってくると、よくこう言われます。
「動かさないと余計に固まるから、どんどん動かした方がいいよ」と。
確かに一理あるのですが、それがいつ・どんな状態でも“正解”とは限りません。
むしろ、タイミングを間違えると悪化させてしまうケースもあります。
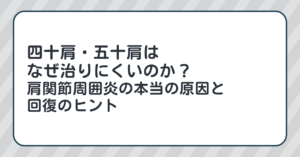
2. 急性期に無理に動かすとどうなる?
肩関節周囲炎の初期は、「炎症期」と呼ばれ、痛みや夜間痛が強く出る時期です。
この時期に無理をすると――
- 筋肉が“防御反応”でさらに固まる
- 神経が過敏になって痛みが強くなる
- 睡眠の質が下がって回復が遅れる
つまり、「動かさないとダメ」という思い込みが、逆に治癒の妨げになることもあるのです。
3. 「動かすこと=動きの再学習」になるように
大事なのは、動かすことが“リハビリ”になっているかどうかです。
ただ動かすのではなく、
- 自分の感覚をちゃんと伴っているか?
- 他の部位との連動を感じられているか?
- 支持面が安定して、安心して動けているか?
こうした**“感覚の条件が整っているか”がカギ**になります。
それがないまま動かすと、「ただ痛いだけ」で終わってしまいます。
4. 感覚 → 動き → 筋力の順番で整える
肩を整えていく上では、次の順番がとても大切です:
- 感覚の再入力(痛くない位置で肩の存在を感じる)
- 動きの再構築(肩甲骨や胸郭との連動をつくる)
- 筋出力の強化(可動域を広げつつ負荷をかける)
つまり、“まず感じる”が最初に来るんです。
いきなり「鍛える」「伸ばす」では、身体がびっくりしてしまいます。
5. 「動かせるけど使えてない肩」になっていませんか?
痛みが落ち着いてきたのに、肩がうまく使えない。
そんなとき、よく見られるのがこの状態です:
- 動かそうとすると他の筋肉が代償的に働く
- 肩甲骨が浮いたままで安定しない
- 動きのタイミングや連動がバラバラ
これは、“動かすことを覚え直す”段階に来ているというサインです。
6. 無理せず“整う方向”に身体を導くことが大切
肩はとても繊細な関節です。
だからこそ、無理に矯正するより、整いやすい条件を整える方が結果的に早いことが多い。
- 呼吸のリズムを整える
- 支持面(接地)の感覚を安定させる
- 肩以外の部位(胸椎や骨盤)を先に整える
これらを通じて、肩そのものを“整う方向”に導くというアプローチが、
安全で効果的な回復の道になります。
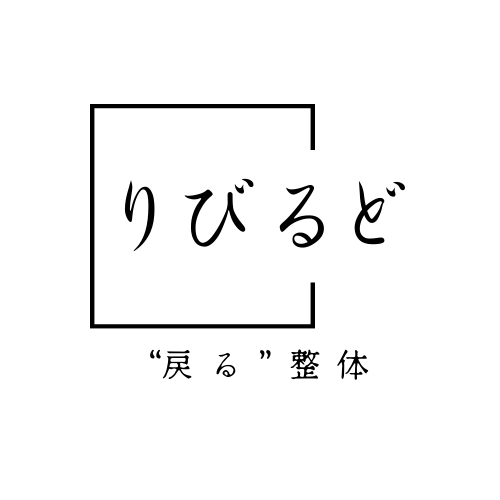
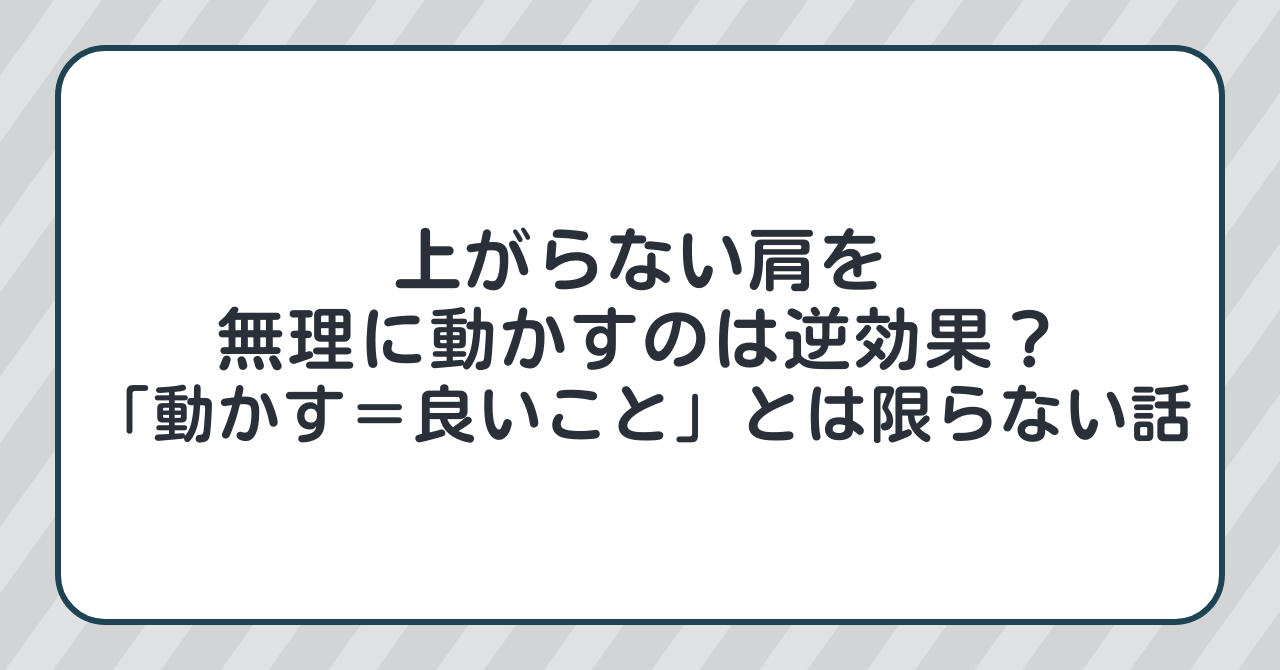
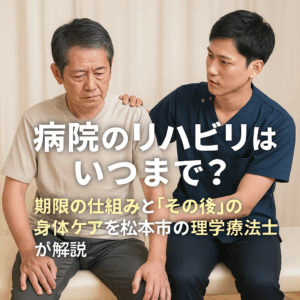


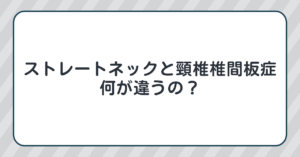
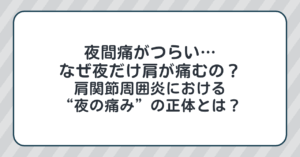
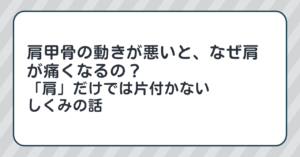
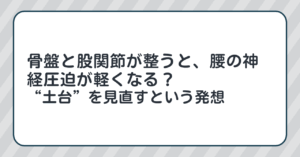
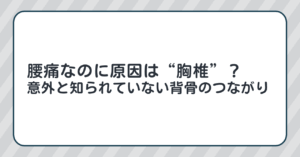
コメント