1. 腰や姿勢の崩れ、実は“坐骨”が感じられていない?
腰痛や姿勢の乱れに悩む方に共通するのが、
「座っているとき、坐骨を感じられていない」という状態です。
坐骨とは骨盤の一部で、お尻の下にある“座るときに接地する骨”。
この坐骨をしっかり感じて座れているかどうかが、実は骨盤や背骨のポジション、さらには腰の負担にまで大きな影響を及ぼしています。
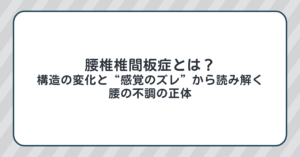
2. 坐骨で座るってどういうこと?
理想的な座り姿勢では、お尻の下にある左右の坐骨が座面に均等に当たり、その真上に背骨がスッと乗っています。
しかし、坐骨の感覚が薄れていると、無意識に骨盤が後ろに倒れたり(後傾)、左右どちらかに偏ったりしてしまいます。
その結果、背中が丸まり、首が前に出て、呼吸も浅くなる――という悪循環が起きやすくなります。
3. なぜ坐骨の感覚が失われてしまうのか?
坐骨の感覚が失われる原因には、以下のようなものがあります:
- 長時間の椅子座り:クッション性の高い椅子やソファでは坐骨の圧覚が鈍りやすく、骨盤が丸まりやすくなります
- 足を組むクセ:骨盤の左右差が固定化され、片側の坐骨が浮いた状態になります
- 姿勢意識のズレ:「背すじを伸ばす」つもりが腰を反らせすぎて坐骨から浮いてしまうことも
これらによって、“坐骨で支える”という感覚が徐々に失われていきます。
4. 坐骨を感じることで骨盤が整う理由
坐骨がしっかり座面に接していると、骨盤が自然に立ちます(ニュートラルポジション)。
この状態では、背骨が本来のカーブを描き、腰椎へのストレスも分散されやすくなります。
逆に、坐骨が感じられないと、骨盤が後ろに倒れたり傾いたりして、背骨のアライメントが崩れ、筋肉が支えの代役を強いられる状態に。
つまり、「骨で支える」感覚を取り戻すことで、「筋肉の頑張りすぎ」が解消されていくのです。
5. 坐骨を取り戻すためのシンプルワーク
▼ ワーク①:坐骨チェック座り
- 硬めの椅子に浅く座る
- お尻を前後左右に小さく揺らして“ゴリッとした骨”を探す
- 左右の坐骨が均等に感じられるポジションでキープ
→ この位置が“骨盤が立つ”感覚のヒントになります
▼ ワーク②:坐骨トントン感覚入力
- 両手の拳で自分の坐骨を軽くトントン叩く(皮膚越し)
- 左右差がないか確認しながら刺激を入れる
→ 皮膚・筋膜・深部感覚への再入力が行えます
6. 坐骨で座れると呼吸・肩・首にも変化が出る
坐骨で座れると、骨盤が立ち、背骨が安定します。
それによって:
- 胸郭が広がりやすくなり、呼吸が深くなる
- 肩の力みが抜けやすくなる
- 首や頭の位置が整い、目の疲れや集中力にも影響
「座り方ひとつ」で、これだけの連鎖が起こるのは、
坐骨が身体の“基準点”のひとつだからです。
7. 「骨で支える感覚」が腰を守る
筋肉を鍛える前に、“骨で支える感覚”を思い出すことが大切です。
坐骨の感覚を取り戻すことで、骨盤の位置が自然と整い、腰への負担が減ります。
腰がつらくなる前に、まずは「坐骨、感じられてるかな?」と問いかけてみてください。
それが、あなたの身体を整える第一歩になるかもしれません。
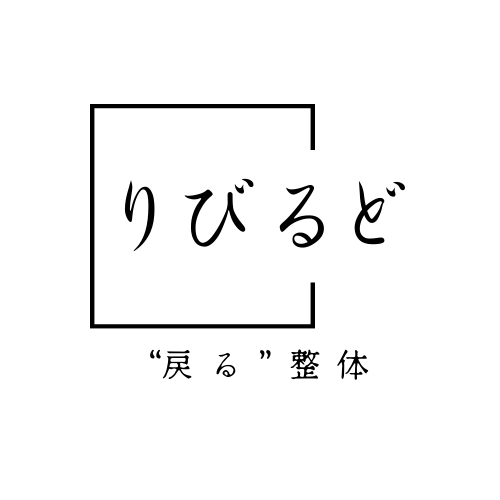
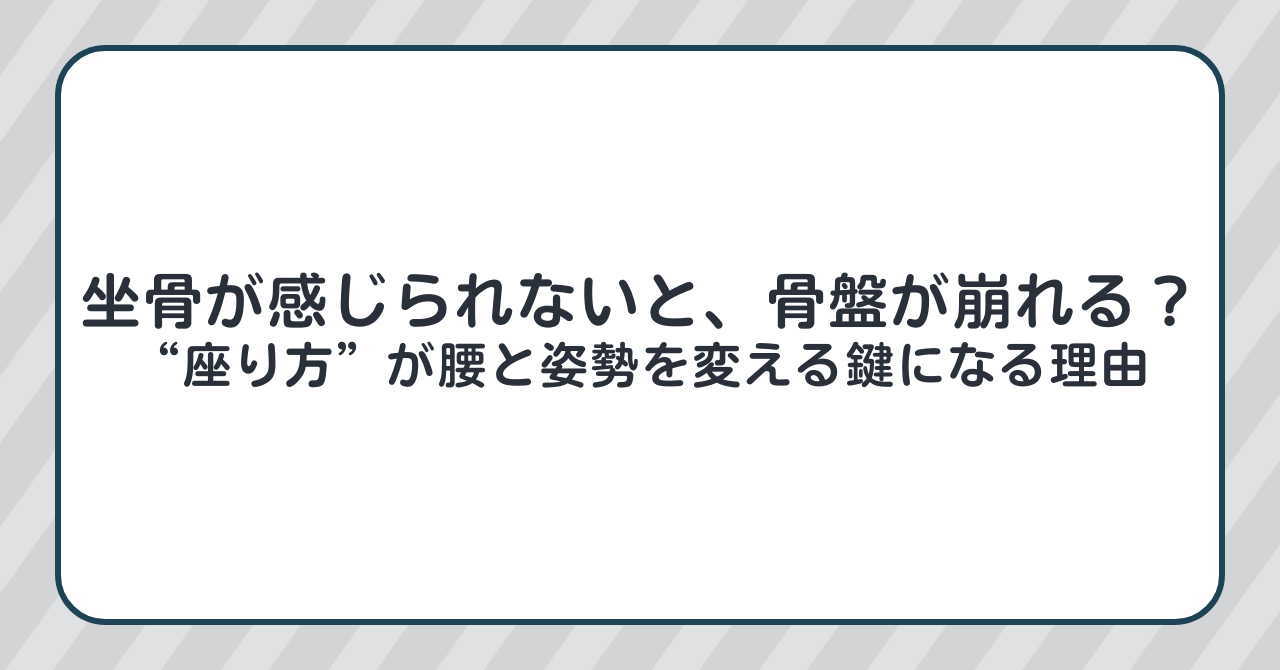
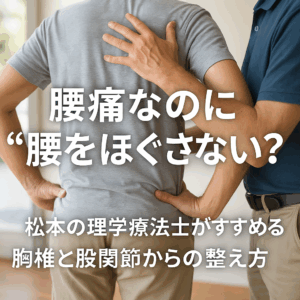

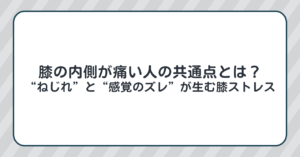
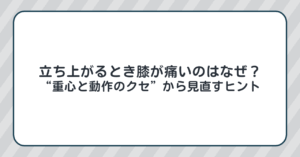
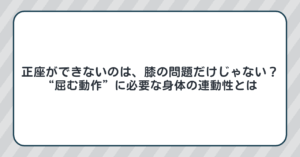
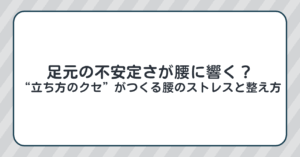
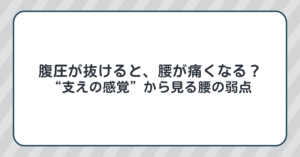
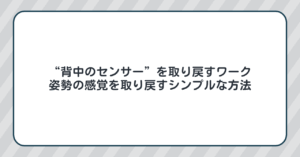
コメント