1. 変形性膝関節症ってどんな病気?
変形性膝関節症(OA)は、膝関節の軟骨がすり減ることで関節の変形や炎症を起こし、痛みや動きの制限が出る疾患です。
日本では中高年女性に多く、特に50代以降で徐々に進行することが多いです。
軟骨の摩耗に加えて、骨の変形や関節包の緊張、滑液の分泌低下など、複数の要素が絡み合いながら症状が進行します。
2. 主な症状は?どんな時に痛みが出る?
- 階段の昇り降りで痛む
- 立ち上がる瞬間にズキッと痛む
- 正座やしゃがみ込みができない
- 膝が腫れて重だるい感じが続く
- 朝起きた直後に動きが固まっている
このように、動き始めや負荷がかかるタイミングでの痛みや、関節の可動域の制限が代表的です。
3. なぜ膝の軟骨がすり減ってしまうのか?
直接の原因は加齢や使いすぎと思われがちですが、実際には以下のような“動きのクセ”や“姿勢のズレ”が関与していることが多いです:
- 重心が外側に偏っている
- 股関節や足関節の可動域が狭く、膝に代償がかかる
- 歩行時に膝がねじれて接地している
つまり、膝単体の問題というよりも、身体全体のつながりの中で“膝に負担が集中するパターン”があるのです。
4. 変形が進んでいても痛みがない人もいる?
実はレントゲンで“変形が進んでいる”と診断された方でも、痛みがほとんどないケースはあります。
その一方で、変形の程度が軽くても痛みが強い人もいます。
この違いは、“身体の使い方”“感覚の鋭さ”“動作時の安定性”などに由来します。
つまり、“変形=痛み”ではなく、
“どのように動いているか”“どう支えているか”が、実際の症状に大きく関与しているのです。
5. ひざに優しい“動き方”とは?
▼ ポイント①:膝を支えすぎない
→ 膝でバランスを取ろうとすると過緊張が起こります。まずは「股関節」と「足裏」の感覚を取り戻すことで、膝への過剰な集中を緩和します。
▼ ポイント②:股関節〜足首の“連動”を高める
→ 膝は中間関節なので、股関節と足首の動きが悪いと代償的に酷使されます。可動域を広げ、スムーズな連鎖を促すことが予防にもつながります。
▼ ポイント③:立ち上がり・階段の“重心誘導”
→ つま先側に軽く重心を移すようにして立つ、階段では踵からでなく母趾球で地面を押すように意識すると、負担が分散されやすくなります。
6. 動かしすぎ?休ませすぎ?バランスが重要
変形性膝関節症では「動かすと悪化する」と不安になり、安静にしすぎてしまうこともあります。
しかし、関節は“動かすことで滑液が循環し、栄養が届く”という構造です。
つまり、負荷をかけすぎずに“正しく動かす”ことが、痛みの緩和と進行予防に効果的なのです。
7. 膝のケアは“構造”と“感覚”の両面から
変形性膝関節症を「治す」ことは難しくても、「悪化を防ぐ」「痛みを減らす」ことは可能です。
そのためには、単に筋力トレーニングをするのではなく、
- 骨盤や足との“連動”を取り戻す
- 膝の“内側からの安定感”を高める
- “支えられている感覚”を再教育する
といった“感覚の再構築”が必要になります。
関節の声に耳を傾けることから、あなたの膝との付き合い方はきっと変わっていきます。
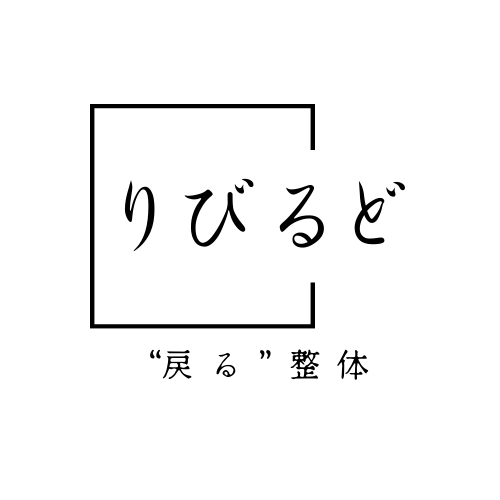
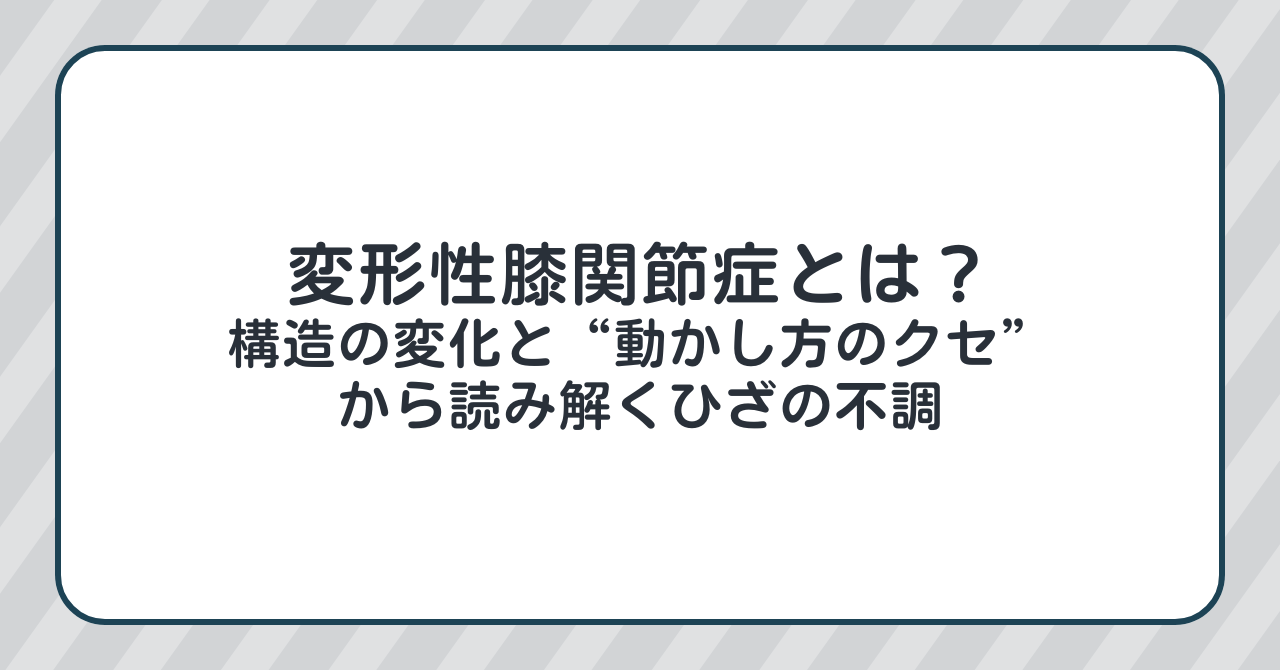
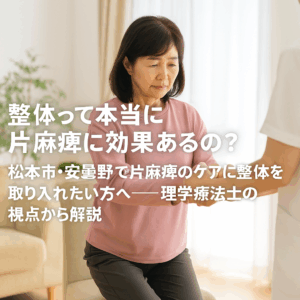







コメント