「整体って、片麻痺にも効果あるんでしょうか?」
私が理学療法士として脳神経外科病院で働いていた時、リハビリを担当した退院間近の片麻痺患者さんからよくそんなご質問をいただきました。
結論からいえば、「すべてのケースに万能ではないけれど、できることは確かにある」というのが、理学療法士としての私の実感です。
たしかに、麻痺という神経の問題は、構造的なアプローチだけで解決できるものではありません。
ですが、片麻痺によって崩れた身体のバランスや感覚のズレを丁寧に整えていくことで、日々の生活動作がグッと楽になることもあります。
今回は「整体が片麻痺にどう関われるのか?」というテーマでお話しようと思います。
脳神経外科病院で片麻痺患者さんのリハビリ経験、整形外科クリニックで整形疾患に悩む患者さんのリハビリ経験、そして整体師として様々な身体の不調に悩む方に施術を行ってきた経験も踏まえつつ、理学療法士としての立場から考えを述べてみます。
参考にして頂けると嬉しいです。

1. 整体は「神経麻痺」そのものを治せるのか?
神経細胞が損傷した麻痺に、整体で“直接的な回復”は難しい
まず大前提として、脳卒中による片麻痺は「中枢神経系の障害」です。
つまり、脳の損傷によって運動や感覚の伝達が正常に行えなくなった結果、手足に麻痺が残っている状態です。
この「神経そのものの損傷」を、整体によって直接的に修復することはできません。
整体はあくまでも“手技による身体機能の調整”を目的とするもので、損傷した脳細胞を治すようなアプローチはできないのです。
では、整体ができることは?
では、整体にはまったく意味がないのか?というと、決してそうではありません。
片麻痺の方の身体には、
- 麻痺側を庇うことで生じた「左右バランスの崩れ」
- 麻痺による「感覚のズレや緊張の高まり」
- 非麻痺側への「過剰な負担と偏った動き」
といった、二次的な問題が数多く存在しています。
整体では、こうした“片麻痺に付随して起こる身体の不具合”に対して、非常に効果的なアプローチが可能です。
筋肉の緊張を整え、姿勢や支持バランスを修正し、感覚の再入力を促すことで、日常動作の安定や痛みの軽減に繋がるケースも多くあります。
2. 片麻痺による“身体の偏り”とは何か?
麻痺による非対称な身体の使い方が、不調の温床に
片麻痺の方は、日常生活の中でどうしても非麻痺側(健側)に頼る動きが多くなります。
歩行・立ち上がり・着替え・トイレ動作など、あらゆる場面で“動きやすい側”に重心を乗せ、支えることが習慣化していきます。
すると、左右の筋肉の使い方に偏りが生じ、やがて「骨盤の傾き」「脊柱のねじれ」「肩の高さの左右差」など、全身のバランスが崩れていくのです。
こうした“偏った身体の使い方”が慢性化すると、
- 腰や膝への痛み
- 転倒のリスク増大
- 麻痺側の動きにブレーキがかかる
といった二次的な問題が発生しやすくなります。

地域特性と組み合わさることで生まれる負担
たとえば松本市や安曇野市のように坂道や段差が多い地域では、非麻痺側への負担がより大きくなりやすい傾向があります。
「麻痺によって偏った身体の使い方」
×
「地域環境による日常動作の負荷」
この組み合わせが、日々の蓄積となって不調を引き起こしているケースは意外と少なくありません。
整体では、身体全体の偏りや緊張のパターンを見直すことで、動きやすさの土台を整えることができます。
3. 整体で実際にできる“アプローチ”とは?
構造のズレや緊張パターンを整える
片麻痺というと、「脳の問題だから整体では何もできないのでは?」と思われがちですが、実はそんなことはありません。
整体では、麻痺によって崩れた身体のバランスや、代償的に過剰に働いている部位の緊張を丁寧にほどいていくことができます。
たとえば…
- 骨盤の歪みや背骨のねじれをソフトに調整
- 非麻痺側の肩や股関節の可動域を広げる
- 麻痺側の皮膚や筋膜をやさしく刺激して感覚を再入力
- 足裏・体幹の感覚を引き出し、“支える感覚”を育てる
これらのアプローチは、あくまで身体の「戻る力」をサポートするもの。
直接麻痺を“治す”ことはできませんが、身体の使いやすさを高めるための土台づくりには大きく貢献できます。
一人ひとりの状態に合わせた“整え方”
片麻痺の方の身体は、回復段階や生活背景によって状態が大きく異なります。
そのため整体では、「決まった手技をやる」のではなく、その方の身体が“今、何を必要としているのか”を丁寧に見極めることが最も重要になります。
整体りびるどでは、麻痺側と非麻痺側の“つながり”を再構築するようなアプローチを重視しています。
それによって、日常生活の動作が少しでも楽に、少しでも安全に行えるようになる――
そんな「実感できる変化」を目指しています。
4. 実際にあった“変化の声”とその背景
「立ち上がりが楽になった」「歩くのが怖くなくなった」
実際に、整体を受けた片麻痺のある方から、次のようなお声をいただくことがあります。
- 「椅子からの立ち上がりで、ふらつかなくなった」
- 「歩いていてつまづくことが減って、自信がついた」
- 「腰や膝の痛みが軽くなって、家の中の移動が楽になった」
- 「麻痺側の足裏の感覚が少しわかるようになった気がする」
こうした変化は、“麻痺そのものが治った”わけではありません。
身体の支え方・感じ方・動かし方に少しずつ「整い」が生まれてきた結果です。
整体は「リハビリ後の身体」にこそ意味がある
病院でのリハビリを終えて自宅に戻った後、「何となく調子が悪い」「でも、どこで見てもらえばいいのかわからない」――
そんな方が実はたくさんいらっしゃいます。
整体は、その“すき間”を埋める存在になれると私は考えています。
- 病院では見切れない、生活レベルでの身体のアンバランス
- 時間の経過とともに強まる、代償的な緊張やクセ
- 痛みや違和感といった“麻痺とは別の不調”
これらに丁寧に向き合い、麻痺があっても“今の身体でできる最適な動き”をサポートするのが整体の役割です。
5. “麻痺があっても動ける身体”を育てていくために
「治す」ではなく「整えて、活かす」ためのアプローチ

整体が片麻痺の回復を“治す”ものだと誤解されることがあります。
ですが本来、整体の目的は「整えることで、今ある身体を最大限に活かすこと」にあります。
- 非麻痺側に頼りすぎてゆがんでしまった姿勢
- 麻痺側を使わなくなったことによる筋緊張や感覚のずれ
- 日々の動作で生まれる不自然な代償パターン
こうした“使い方のクセ”を少しずつほどきながら、本来の感覚と動き方を思い出すように整えていく――
それが、整体にできることだと私は考えています。
「片麻痺だからこそ、自分の身体を整える意識が大切」
麻痺があるからこそ、身体の声に耳を傾ける必要があります。
痛みや違和感は「気合いで乗り切る」ものではなく、“整えてほしい”というサインでもあります。
松本市や安曇野市のように坂道や段差の多い地域では、ほんのわずかな身体のズレが、毎日の移動や生活に大きく影響します。
だからこそ――
整体で“今ある身体の最適な状態”を育てながら、
自分自身の身体とじっくり向き合っていくこと。
この視点こそが、片麻痺とともに生きるうえで大切な「整える力」につながっていくのではないでしょうか。
最後までお読み頂きありがとうございました。
整体りびるどでは、片麻痺ケアに悩む皆様のご相談をお待ちしています。
お気軽にお問い合わせください。
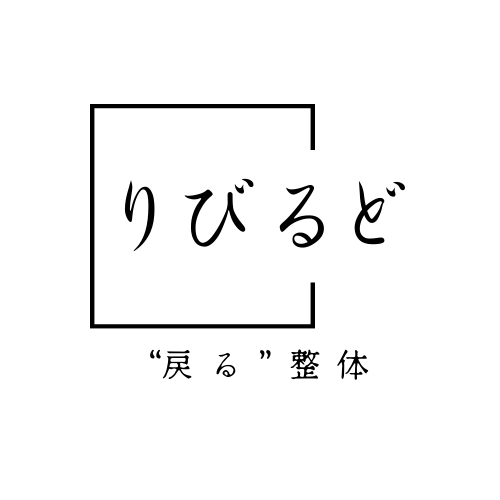
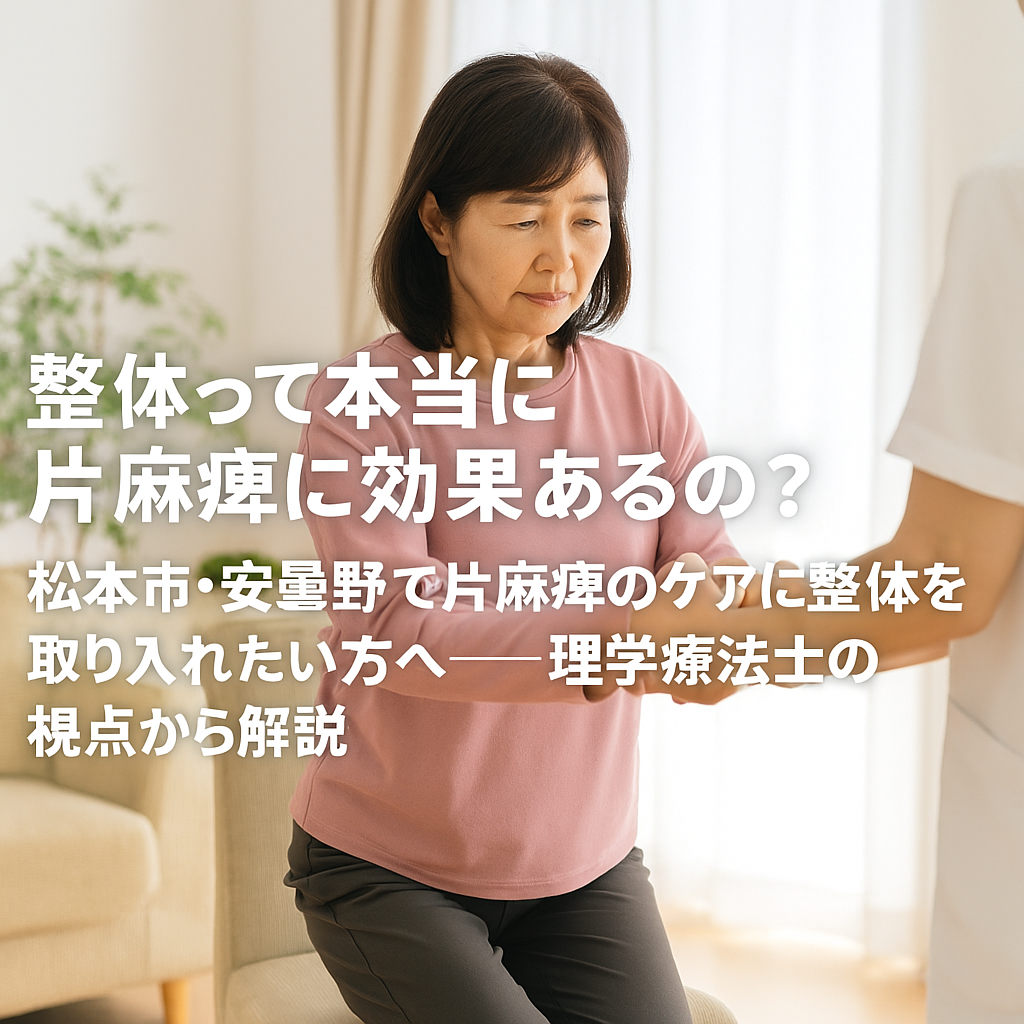






コメント