1. なぜ“膝の内側”に痛みが集中するのか?
膝の痛みの中でも、特に多いのが「内側の痛み」。
歩くとズキッとする、階段を降りるときにピリッとくる、膝を押すとズーンと響く。
これらは変形性膝関節症の初期にもよく見られますが、実際には「膝の内側だけが悪い」というより、身体の動きや感覚の偏りによって“負担が集中している”状態が多いのです。
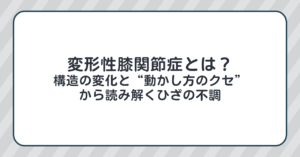
2. 内側に負担が集中する3つのメカニズム
① 下腿(すね)の外旋が強い
→ 歩行時や立位で、足が外に向くクセがあると、膝関節が内側にねじれ、内側に圧が集中します。
② 股関節の内旋制限
→ 股関節が内に入らないために、膝が内側へ入り込み、結果として内側支持組織にストレスがかかります。
③ 足裏重心のズレ(外側荷重)
→ 足裏の外側に体重がかかることで、膝がX脚傾向になり、内側に負荷がかかるパターンです。
3. 関与するのは“構造”と“感覚”の連鎖
膝の内側の痛みは、関節構造そのものの変化だけでなく、
“どう動いているか”“どう支えているか”によって決まります。
また、「どこを感じて、どこを感じられていないか」という**“感覚の地図の偏り”**も見逃せません。
たとえば、足裏の内側アーチや母趾球の感覚が鈍い人ほど、外側に逃げやすく、膝の内側で支えようとする代償が強くなります。
4. 膝の内側痛を生む“ねじれパターン”とは?
立っているときや歩いているとき、身体は常に“ねじれ”を伴って動いています。
このねじれが適切に解放されず、膝関節で止まってしまうと、関節内に過剰な剪断力が発生しやすくなります。
- 足先が外向き+膝が内向き → 内側に圧縮ストレス
- 股関節が動かない+膝で代償 → 半月板や内側靱帯への圧
こうした“動作のねじれ”が、膝の内側を繰り返し刺激してしまうのです。
5. まずは“足裏感覚”を取り戻すところから
▼ ワーク①:3点支持リセット
- 素足で立ち、母趾球・小趾球・かかとに均等に乗る感覚を確認
- 外側だけに体重が偏らないよう注意
→ 足裏の感覚が整うと、膝の軌道も安定します
▼ ワーク②:内くるぶし感覚スライド
- 立位で膝を軽く曲げ、内くるぶし同士を軽く近づける意識
- 膝が内に入りすぎず、股関節からの動きを引き出せると◎
6. 膝だけじゃない。“股関節と足”がカギ
股関節と足関節の動きがスムーズだと、膝は“通過点”としての役割を果たせます。
逆に、上(股関節)と下(足首)が硬いと、膝がその“しわ寄せ”を受けてしまいます。
- 股関節:外旋・内旋のバランスが悪い
- 足首:背屈や回内の動きが少ない
こうした状態では、膝の内側に“逃げ場のない力”がかかり続け、炎症や慢性痛に繋がりやすくなります。
7. “感じる場所”を変えれば、膝は変わる
膝の内側が痛むとき、「構造をどうにかしよう」と考えがちです。
でも、感覚のズレや重心の偏りといった**“自分の感じ方”**を変えることが、結果的に膝への負担を減らす近道になります。
あなたは今、足裏のどこを感じて立っていますか?
膝で踏ん張っていませんか?
そんな問いかけが、痛みを“変えていく感覚”のスタートになるかもしれません。
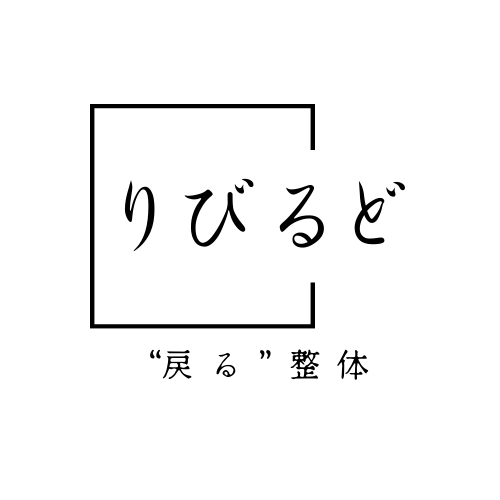
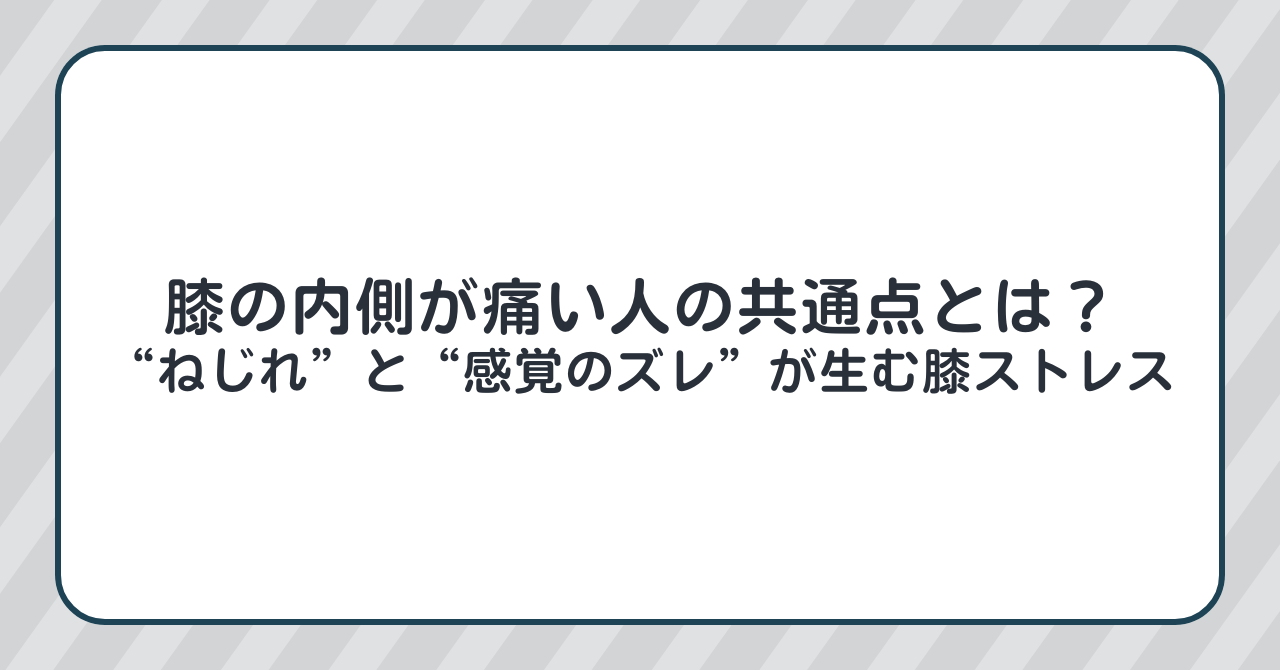
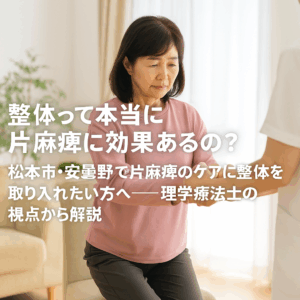







コメント