1. 腰が痛いとき、“腰以外”を見るのはなぜ?
腰が痛い、足がしびれる、動くたびに不安がある…。
こうした症状があると、つい腰そのものを疑いたくなります。
けれど実際には、「腰だけに注目しすぎると、本質を見失うことがある」んです。
なぜなら、腰は**“中継点”であり、“土台”ではない**からです。
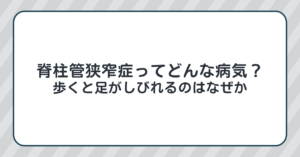
2. 骨盤と股関節が動けば、腰はがんばらなくていい
私たちの身体は、**足 → 股関節 → 骨盤 → 背骨(腰)**というふうに連動して動いています。
でも、どこかが動きにくくなると、その上の部分が“がんばる”ようになります。
たとえば――
- 股関節が硬くてうまく曲がらない
- 骨盤が前傾・後傾で安定していない
- 片足立ちが苦手で、左右差が大きい
こうした状態では、腰が過剰に動かざるを得なくなり、結果として神経に負担がかかるのです。
3. 神経圧迫は「構造」だけが原因ではない
「脊柱管が狭くなっているから神経が圧迫されている」
それは一つの見方ですが、それだけでは説明できないケースもたくさんあります。
実際には、
- 神経の周囲組織(筋・靭帯・筋膜)の緊張
- 滑走性の低下(神経がスムーズに動けない)
- 体幹のアンバランスによる“一点集中の負荷”
など、“構造+動作+感覚”のトータルで見ないと本当の原因にたどり着けないことが多いのです。
4. 骨盤と股関節の「整い方」は感覚で変わる
整える=位置を揃える、だけではありません。
「どう感じて」「どう使えているか」こそが本質です。
- 股関節を動かすとき、ちゃんと“はまって”いる感覚があるか
- 骨盤が支えとして“どっしり安定”しているか
- お尻や内ももの筋肉が“反応する感覚”があるかどうか
こうした“感覚のフィードバック”が整うと、腰への負担が自然と軽くなるのです。
5. 結果ではなく、“前提”を整える
腰にかかる負担は、「結果」にすぎません。
その負担をどう回避するか?という視点では、“前提”を変える必要があります。
- 重心の位置
- 地面の踏み方
- 股関節の受け皿感
- 骨盤の安定性
これらが整うと、腰を無理に支えなくても動ける身体に変わっていきます。
6. 「整える」とは、動きの余白を取り戻すこと
腰の神経が圧迫されているように感じると、「もう動かしちゃいけない」と思いがちです。
でも本当は、「他の場所がうまく使えていないから、腰だけががんばっている」ことが多い。
骨盤と股関節を“整える”とは、腰にかかっていた仕事をみんなで分担するようにすること。
身体の中に余白=選択肢が生まれれば、神経のストレスは自然と減っていきます。
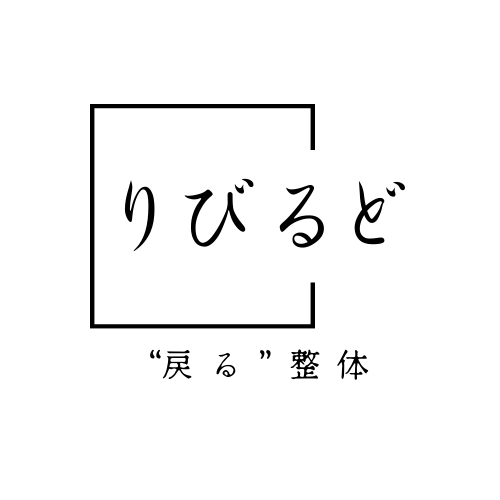
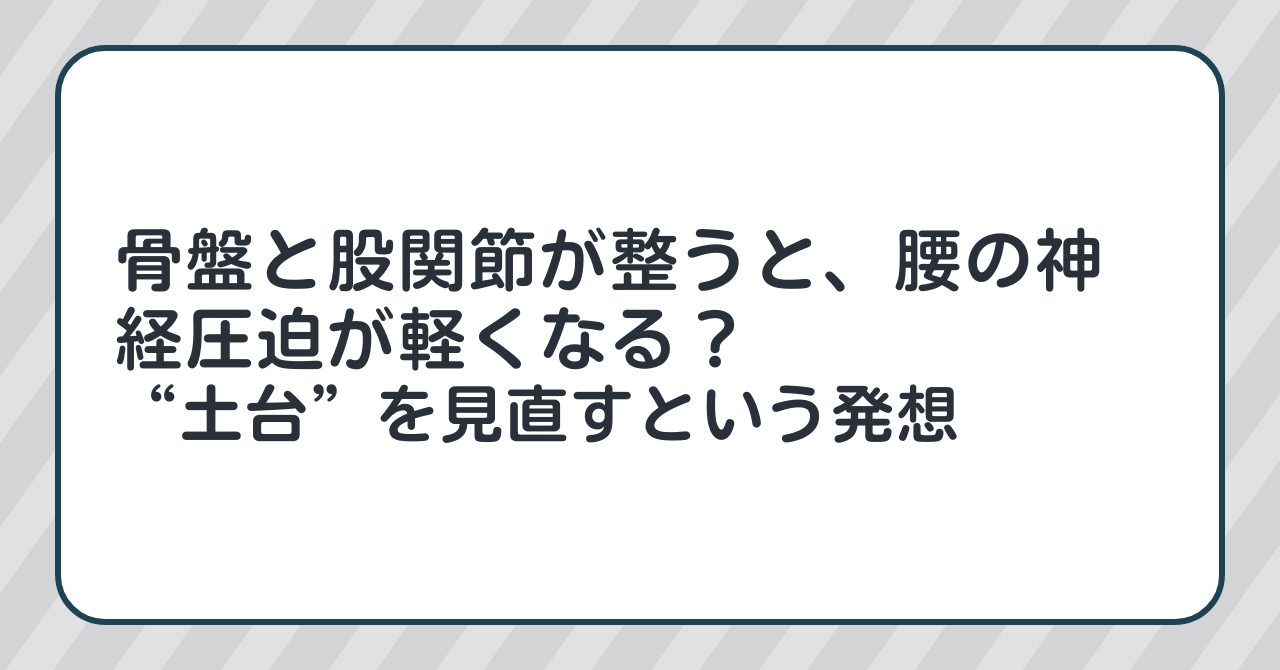
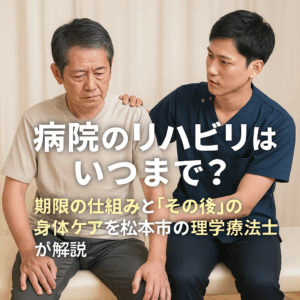


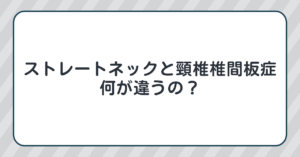
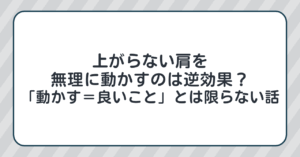
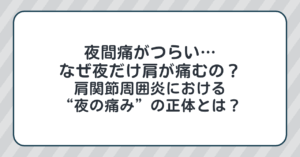
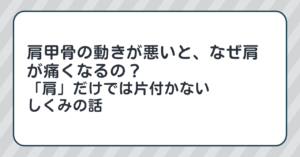
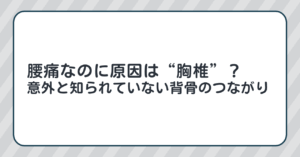
コメント