退院後、「なるべく麻痺側の手足も使いましょう」と言われたものの――
実際には「うまく動かない」「ぎこちなくて怖い」「つい非麻痺側ばかり使ってしまう」…そんな悩みを抱えていませんか?
「使ったほうがいいのは分かっている。でも、それが難しい。」
この葛藤には、身体的な理由だけでなく、感覚のズレや心理的な壁が複雑に関係しています。
今回は、“麻痺側をうまく使えないのはなぜか?”という問いに、専門的な視点から丁寧にお答えしていきます。
その上で、日常生活の中でできる小さなステップやケアのヒントもお伝えします。

1.「使えない」の正体はどこにある?
麻痺とは「完全に失われた」わけではない
脳卒中後の片麻痺と聞くと、「もうその手足は使えない」と思い込んでしまう方も少なくありません。ですが実際には、“まったく動かない”わけではなく、「少し動くけれど不器用」「感覚が分かりづらい」といった中間的な状態にある方がほとんどです。
これは、脳からの指令が筋肉へ正確に伝わりづらくなっているためで、構造的な問題というよりも神経系のつながりや感覚の認識の問題が背景にあります。
感覚のズレが「怖さ」や「違和感」を生む
もうひとつ大きな壁となるのが、“感覚の不一致”による不安感です。
たとえば、自分では手を伸ばしているつもりでも、実際には違う方向に動いている…そんなズレがあると、無意識に「この手は怖い」と感じ、使用を避けるようになります。
このように、「使えない」という感覚は、**“使わなくなっていった結果”**であることがとても多いのです。だからこそ、身体の状態を正しく理解し、“使える可能性”を取り戻すアプローチが重要になってきます。
2. “感覚のズレ”が、身体の動きを止める理由

「自分の手足が自分のものじゃない」感覚
片麻痺のある方がよく口にされるのが、「麻痺側の手や足が、自分のもののように感じられない」という違和感です。これは、脳がつくり出す“身体地図(ボディマップ)”が乱れている状態。
本来あるべき感覚入力(皮膚感覚や関節位置の情報)が減ったりズレたりすると、脳が“その部位をうまく認識できない”のです。
結果として、「動かすのが怖い」「どのくらい力を入れればいいか分からない」といった不安が積み重なり、身体を動かす意欲そのものが低下していきます。
意識して動かそうとするほど、うまくいかない
感覚のズレがあると、脳は過剰に注意を向けるようになります。たとえば、手を伸ばすときに「指はどうなっている?」「肩は?」と細かく意識しすぎることで、逆に動きがぎこちなくなったり、緊張が強くなったりしてしまうのです。
これは、まさに“感覚と運動の協調”がうまくいっていないサイン。
つまり、「動かせない」のではなく、“動かしづらくなっているだけ”というケースが非常に多いのです。
3. 「使えない」から「使ってみよう」へ:動きを取り戻す3つのヒント
― ヒント①:動かす前に“感じる”時間をつくる
感覚のズレがあるときは、いきなり「動かそう」とするのではなく、まず**“触れる・感じる”ことを優先**しましょう。
たとえば、麻痺側の手のひらを反対の手で包み込み、温かさや重さをじっくり感じてみる。
たったこれだけでも、脳内の身体イメージが少しずつ“つながり直す”きっかけになります。
― ヒント②:“動かすこと”より“動きを思い出すこと”
「動かす」ことに意識が集中しすぎると、無理な力みや緊張につながってしまいます。
それよりも、「昔はこうやって歩いていたな」「こうやって手を挙げていたな」という記憶を呼び起こすような意識で動作に入ると、神経系はより自然に動きを再構成しやすくなります。
― ヒント③:小さな成功体験を繰り返す
「できた」「わかった」という小さな達成感が、脳にとっての何よりのご褒美です。
麻痺側の手でコップを支えるだけでも、「今日はここまでできた」とポジティブに捉えることが、継続のモチベーションになります。
自分を責めず、変化の芽に気づくことが、回復への一歩です。
4. 現場で実践している「麻痺側を使うための工夫」
無理に“使わせない”。まずは「気づき」を引き出す
臨床では、いきなり「麻痺側をたくさん使いましょう」とは言いません。
むしろ、“使えない状態”の理由を一緒に探ることから始めます。
たとえば「足の裏に体重がうまく乗っていない」「腕の位置感覚がずれている」など、“気づき”を丁寧に引き出すアプローチが、第一歩になります。
“感じやすい場所”を起点に動きを誘導
感覚の入りやすい部位(例:手の甲、足裏、肩甲骨)を使って動きのヒントを入力すると、麻痺側も動きやすくなることがあります。
これは「皮膚刺激→姿勢調整→動作誘導」という神経系の働きをうまく活用した方法で、無理に動かすのではなく、“動きやすくなる環境”を整えるという考え方です。
“両側の協調性”を引き出す運動がカギ
麻痺側だけを一方的に使わせようとすると、かえって緊張が高まることもあります。
そのため、非麻痺側と麻痺側を同時に使う“左右協調”の動作練習を取り入れることで、自然な流れで麻痺側も動き始めるようになります。
実際の現場では、こうした視点を織り交ぜながら、一人ひとりの身体の状態に合わせた“使いやすくなるきっかけ”を探っていくことが、何より大切です。
6. “できない”じゃなく、“まだ慣れていないだけ”
自分を責めずに、もう一度向き合う
「やろうと思ってもできなかった」「何度もチャレンジしたけど続かなかった」
そんな経験がある方も、どうか自分を責めないでください。
麻痺側の手足が使いづらいのは、“意志が弱いから”でも“努力が足りないから”でもありません。
それは、脳と身体のつながりが一度途切れたことによる“自然な戸惑い”であり、そこから回復していくには“時間”と“適切なサポート”が必要なのです。
「戻す力」は、あなたの中にある
あなたの身体には、本来の動きを思い出す力=“戻す力”が備わっています。
ただその力をうまく引き出すには、ちょっとした「きっかけ」や「感覚の再発見」が必要なのです。
今回お伝えした内容が、その小さなきっかけになれたのなら、とても嬉しく思います。
一人で抱え込まないでください
もし今、あなたがどこかに不安や迷いを感じているなら――
身体の状態、動かし方、感覚の違和感、どんなお悩みでも構いません。
まずはお気軽にご相談ください。
整体りびるどは、いつでもそんなあなたの「助けて」に寄り添います。
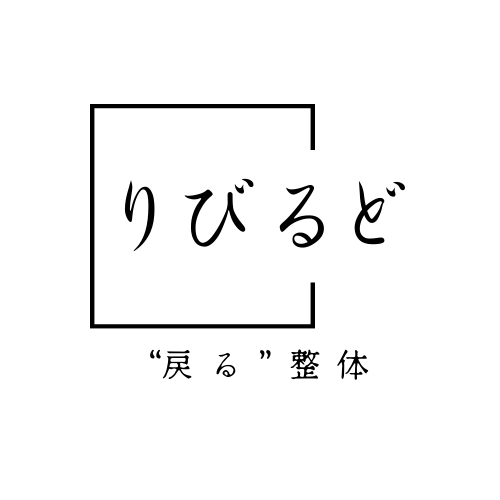
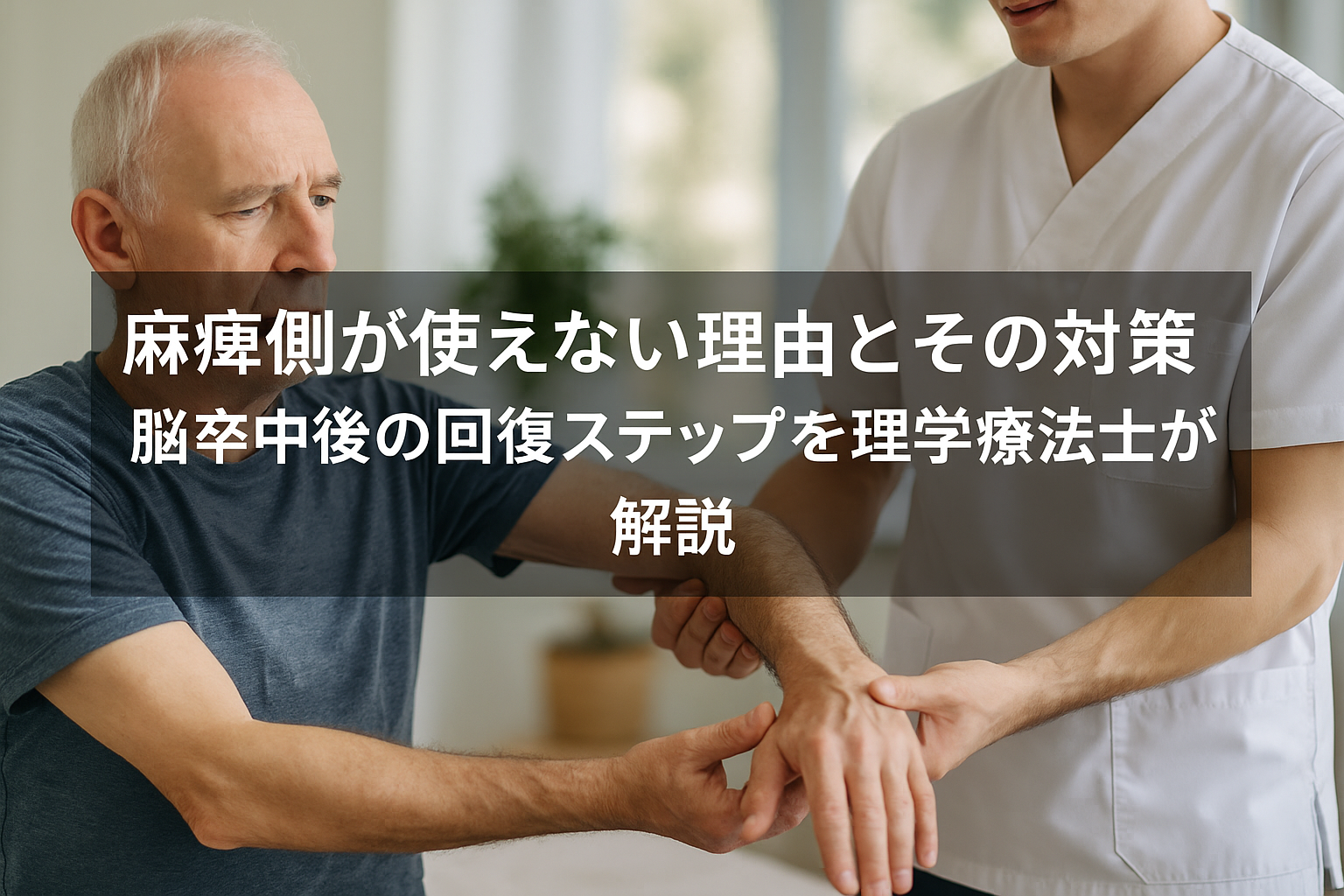
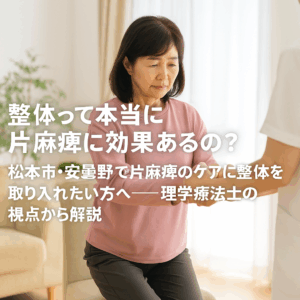






コメント