1. ストレートネックって何?
本来、首(頸椎)は前方にゆるやかなカーブを描いています。
このカーブがあることで、頭の重さ(およそ5〜6kg)をうまく分散し、首や肩の筋肉への負担を減らしています。
しかし、スマホやパソコン作業が日常化し、うつむき姿勢が習慣になると、このカーブが失われていきます。
首がまっすぐ、あるいは後ろに反るような状態になってしまう――これがストレートネックです。
最近では10代〜20代の若年層でも多く見られ、「スマホ首」と呼ばれることもあります。
2. ストレートネックがもたらす身体への影響
ストレートネックになると、頭が胴体の真上から前にズレてしまい、首と肩の筋肉が絶えず頭を支え続ける状態になります。
特に負担がかかるのが以下の筋肉です:
- 僧帽筋(そうぼうきん)
- 肩甲挙筋(けんこうきょきん)
- 胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)
これらの筋肉が慢性的に緊張すると、肩こり・首こり・頭痛・眼精疲労などが起こりやすくなります。
また、筋肉の張りだけでなく、神経の過敏化や感覚のズレも引き起こしやすくなります。
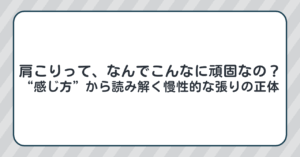
3. 姿勢と連動する「首のカーブ」
「ストレートネックは首の問題」と思われがちですが、実際は全身の姿勢との関係が深いです。
たとえば:
- 骨盤が後ろに傾くと、背中が丸まり、首が前に出やすくなる
- 胸椎が硬くなると、首でバランスを取ろうとする
- 足裏の接地感が薄いと、姿勢が安定せず、頭が前方にシフトしやすくなる
つまり、全身のアライメント(身体の整列)が崩れた結果、首のカーブが変化するというケースが非常に多いのです。
4. 感覚と構造のズレが肩こりを長引かせる
ストレートネックでは、見た目の姿勢以上に、“感覚のズレ”が問題になることが多いです。
- 頭が前に出ている状態を“普通”と感じてしまっている
- 肩をすくめていることに気づいていない
- 背中や首の皮膚感覚が鈍くなっていて、自分の姿勢が分かりづらい
このような状態では、筋肉や関節を整えるだけでは不十分。
「今の自分の状態を感じ取り直す」=感覚の再構築が、肩こり改善のカギになります。
5. 呼吸・足裏・骨盤――首を支える“3つの土台”
ストレートネックと肩こりに悩む人の多くに共通するのが、首を支える土台の不安定さです。
その土台とは――
【呼吸】
- 呼吸が浅くなると、胸郭が広がらず、背中が硬くなる
- 首や肩を使って呼吸するクセがつき、常に力が入りやすくなる
【足裏】
- 地面をしっかり踏めないと、全身の姿勢がグラつき、頭部の位置が安定しない
- 重心が後ろにズレると、頭が前に出てバランスを取ろうとする
【骨盤】
- 骨盤が後傾すると、脊柱全体が丸まり、首の位置もズレやすくなる
- 骨盤の安定性が、首・肩の負担軽減の出発点になる
つまり、首を整えるには、首だけを触るのではなく、身体全体の“支え”を整える必要があるのです。
6. ストレートネック=悪ではない。「動ける首」を目指す
「ストレートネック=悪い」と思われがちですが、
実際にはストレートネックでもまったく不調が出ない人もいます。
重要なのは、**首が“どう見えるか”より、“どう使えているか”**です。
- 力を抜いたときに、頭の重さを感じられるか?
- 呼吸や歩行の中で、首が自然に動いているか?
- 首の前後左右の筋肉がバランスよく働いているか?
このように、“働ける首・動ける首”に戻していくことが、肩こり解消につながります。
7. 「首に責任を押しつけない」整え方を
肩がこると、つい首や肩をマッサージしたり、ストレッチしたりしたくなりますよね。
でも、なかなかスッキリせず、「また戻ってしまう」ことが多いのではないでしょうか。
それはきっと、首が“がんばらされている”状態が改善されていないからです。
- なぜ首が過緊張しているのか?
- 首以外のどこが“支えられていない”のか?
- 自分の姿勢や呼吸、感覚はどうなっているのか?
このように、**“首に責任を押しつけない整え方”**こそが、慢性肩こりからの脱却につながります。
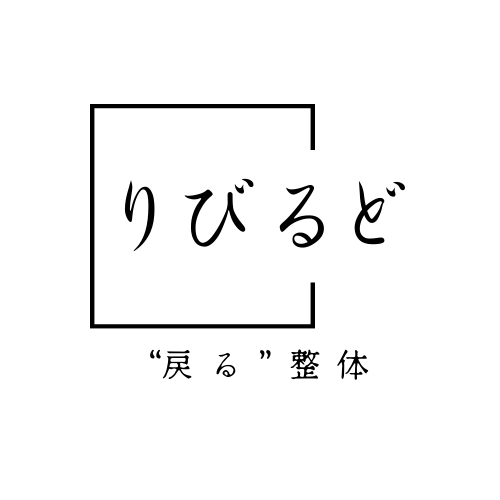
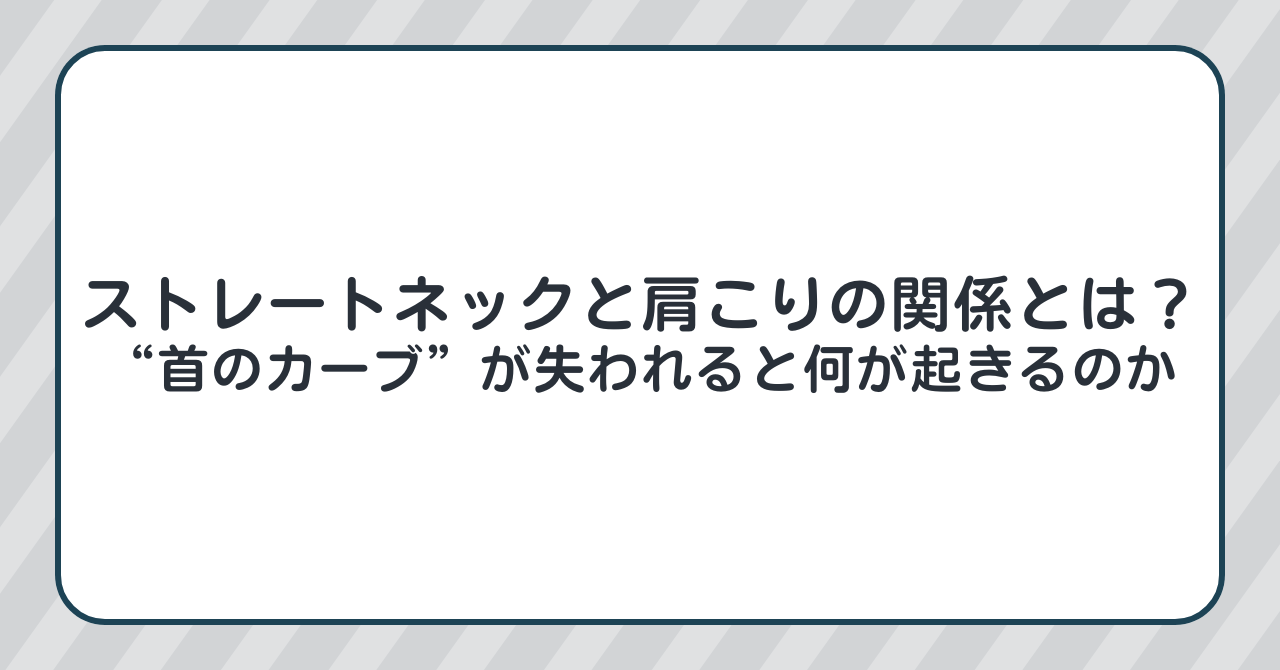
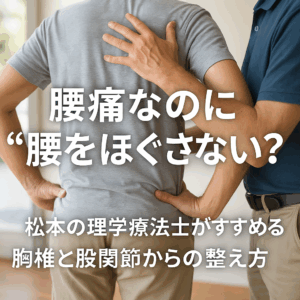

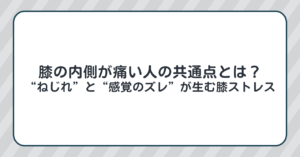
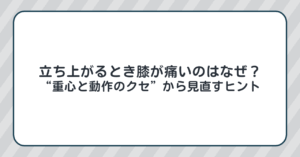
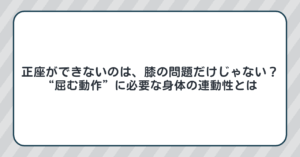
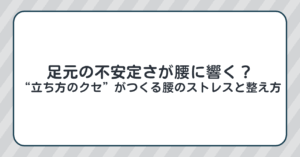
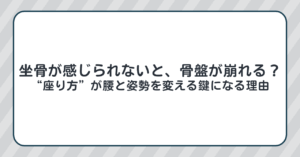
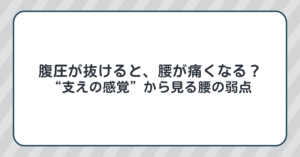
コメント