どうも。整体りびるど代表、理学療法士のテラサワです。
今回は、脳卒中後の片麻痺ケアを“続けたくても続けられない”という方へ、というタイトルで記事を書かせて頂きました。
脳卒中を経験された多くの方が、病院でのリハビリを経て一度は「動けるようになった実感」、「まだまだ改善していくであろう手ごたえ」を感じます。
しかしながら、病院で行えるリハビリには制度の制限や期限という壁が存在しています。
「制度の制限や期間の壁により、もっと続けたいのに打ち切られてしまった」
理学療法士として働いていると、そんな声を様々なところで耳にします。
とくに松本市や安曇野市のような地域では、リハビリ終了後に「どこで」「誰に」「どうやって」身体のケアをしてもらえばよいのか、情報が少なくて戸惑う方も多いのではないでしょうか。
私は合計で10年近く松本市の脳神経外科病院で働いていた経緯があります。
病院でリハビリを行っていた頃は希望を抱きながら日々を一生懸命過ごしていた患者さんが、回復期の病院に転院し、その後退院。
「自宅へ戻ってから、続けたいリハビリを続けられず途方に暮れてしまった、もう半分諦めている…」
そんな生の声を何度も直接聞いてきました。
片麻痺による動きのクセやこわばりは、放っておくと少しずつ進行し、痛みや日常生活の負担として現れてきます。“もう治らない”と思って諦めるのではなく、“まだ動きたい”という気持ちを大切にしてほしい。私はそう考えています。
この記事では、「リハビリが終わった後も、身体と向き合い続けたい」と願うあなたに、そしてそんなあなたを大切に考えているご家族様に向けて、医療や介護とは違うもう一つの選択肢をご紹介していきたいと思います。
1. 病院でのリハビリが終わったら、どうすればいいの?
病院のリハビリには期限がある
「脳卒中のリハビリは、だいたい180日までです」
病院でそう説明されたことがある方も多いかもしれません。
医療保険制度では、回復期の入院リハビリにも在宅での外来リハビリにも期限や日数制限が設けられています。
もちろんその制度は、全国の限られた医療資源を守るために必要なものです。けれど、現場で理学療法士として働いていると、いつも胸が痛くなる場面があります。
それは、「本人の中にはまだ明らかに回復の余地がある」のに、「制度の上ではもう十分」という理由でリハビリが終了してしまうケースです。
患者さんもご家族も、「まだリハビリを続けたい」「せっかくここまで頑張ってきたのに」と悔しい思いをされることが少なくありません。
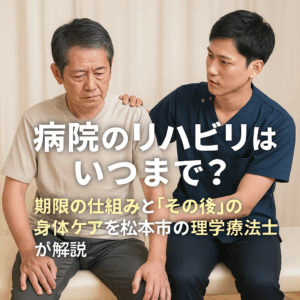
“医療のリハビリ”と”介護”のリハビリ
もちろん、これは病院を退院したら完全にリハビリが打ち切られる、という意味ではありません。
病院で受けるリハビリはあくまで「医療」の枠でのリハビリであり、一般的に、「医療」の枠でのリハビリがひと段落したら次は「介護」の枠でのリハビリに移行します。
いわゆる、介護保険で受けるリハビリです。訪問リハビリや通所リハビリがこれにあたります。
ただ、「介護」の枠で行うリハビリはあくまで“機能維持”や“自宅での生活を行いやすくする”ことに主眼が置かれるため、病院のリハビリを意欲的に行ってきた患者さんにとっては物足りなさを感じる方も多くいらっしゃいます。
“望む支援”を受けることの難しさ
病院を出たその後、本当はまだ“機能改善を見据えたケア”が必要な状態なのに、“ご本人様が望む支援が受けられない”という空白期間が生まれてしまう。
これは、地域で暮らす上での見えにくい課題のひとつです。
とりわけ松本市や安曇野市などの地方都市では、都市部などと比べるとさらにそういった傾向が色濃く見られます。
でも、本当にそこで終わってしまっていいのでしょうか?
動けるようになってきたからこそ、「そこから先」を支える環境がもっと必要だと私は考えています。
2. “片麻痺”は、そのままにしておくと悪化することも
脳卒中後の障害は片麻痺だけとは限らない

脳卒中後の片麻痺において、「退院できた=もう大丈夫」というわけではありません。
退院時には見た目に大きな障害がなくても、“感覚が鈍いまま、関節の動きが硬いまま”といった状態が実は残っており、それを放っておくと日常生活の中でじわじわと不具合が積み重なってきます。
例えば、肩や肘のこわばりによって更衣動作がしづらくなる、足の運び方に偏りが出て膝や腰に痛みが出てくる、軽度の麻痺によって手足の連動がうまくいかない――
これらはよくある“あるある”ですが、放っておくと二次障害(関節拘縮・筋萎縮・慢性痛など)に発展するリスクをはらんでいます。
脳卒中と整形疾患の関連性
脳卒中後は、片麻痺症状に注目されがちですが、身体が上手く使えないことで様々な関節や筋肉に負担がかかりやすくなる、という点は、想像に難くありません。
それはつまり、”健常な人よりも筋肉や関節の問題が生じやすくなる”ということ。麻痺側をかばい続けることで健側の膝や腰などに痛みや関節障害が生じることも多く、Verheydenら(2008)の研究では、体幹や非麻痺側の使い方が予後に大きく関わると示唆されています※1。
肩関節周囲炎、変形性膝関節症、脊柱管狭窄症など整形外科領域のこういった病名は一見、脳卒中と関わりは薄いように感じますがそんなことはありません。
実際、病院で片麻痺の患者さんのリハビリをしながら、麻痺以上にこういった疾患の症状に悩まされることは何度もありました。

麻痺側を”使う”難しさ
そして特に片麻痺の方に多く見られるのが、“使えないから使わない”という負のサイクルに陥ってしまうことです。
麻痺側の手足は「なるべく使うようにしましょう」とは言われるものの、感覚のズレや細かい動作のぎこちなさがあると、つい非麻痺側に頼った生活スタイルが習慣化してしまいます。
そして、“動かさないことでますます動きづらくなる”という悪循環が進行していきます。


小さな変化に目を向けるために必要な専門的な”視点”
片麻痺の身体には、“少しずつズレていくような変化”が静かに起きています。
その変化を本人が実感しにくいからこそ、定期的に身体の状態を確認し、必要に応じてケアしていくことがとても大切なのです。
そしてそういった後遺症ケアを適切におこなうためには、”脳卒中に関する知識や経験”と、”整形疾患に関する知識や経験”を併せ持った指導者・セラピストが必要不可欠です。
病院を出たあとも、自分の身体にちゃんと目を向けていける場所――
それが、いま求められているのではないでしょうか。
松本市や安曇野市の方が気軽に足を運べるそんな場所。
整体りびるどこそそういった場所になるべきだと、私は考えています。
3. “もう動けない”じゃなくて、“どう動かすか”を見直すタイミング
回復速度の低下=”回復できない”じゃない
「もうこれ以上、動けるようにはならないんだろうな」
退院後、そんな風に感じてしまう方も少なくありません。
確かに、脳卒中発症から数か月が経つと、周囲からも「もう落ち着いたね」と言われることが増え、回復の実感が薄れていく時期に差しかかります。
けれど、それは「もう回復できない」ことを意味するわけではありません。
むしろ、ここからは**“どう動かすかを見直すタイミング”**だと私は考えています。
重要なのは動きの再認識
脳卒中後の身体は、脳の損傷によって“動かし方を忘れてしまった状態”にあります。
つまり、筋肉がないわけでも、関節が壊れたわけでもなく――感覚と運動のつながりがうまく働いていないことが多いのです。
だからこそ、片麻痺患者さんは「筋トレを頑張る」「たくさん歩く」といった努力よりも先に、運動学習による“自分の身体がどう動いているか”を再認識する感覚づくりが必要になります。
これは、理学療法士として多くの片麻痺患者さんと関わる中で一貫して感じてきたことです。
視点を変えれば”動き”も変わる
実際、脳には「可塑性(plasticity)」という性質があります。
これは、神経同士のつながりが新たに生まれ直す力のことを指し、年齢に関わらず刺激次第で変化が起こせることが分かっています※2。
つまり、「もう動けない」ではなく、「新たな動かし方を再学習する」という視点に切り替えることが、回復の鍵になります。
この視点を持てるかどうかで、退院後の身体の変化はまったく違ったものになります。
病院を出た“その先”の時間を、あきらめの延長ではなく、新しい動きとの出会いの場にできるかどうか――
そこに本当の意味でのケアの価値があると、私は信じています。
4. 松本・安曇野で“継続できるケア”を探している方へ
自分に合ったケアの”場”を見つけるのは難しい

病院でのリハビリが終わっても、身体のケアは一生続けていくもの。
そう感じている方ほど、「じゃあ、どこで、誰に、どんなサポートを受ければいいのか?」という迷いにぶつかります。
松本市や安曇野市のような地域では、回復意欲のある方が「次に進む場所」を見つけづらいという現実があります。
通所リハビリや訪問リハビリはあっても、「今の自分の身体をもっと理解して、変えていきたい」というニーズにぴったり合う場は決して多くありません。
片麻痺のケアは”専門的な知識や経験”が必用
では、「整体」や「パーソナルトレーニング」はどうかというと――
たしかに、身体を整える手段としては存在します。ただし、脳卒中後の片麻痺という特殊性に対応できるかどうかは、提供者の専門性によって大きく差が出るのが実情です。
片麻痺の身体には、筋肉や関節だけではなく、感覚・反射・神経系の微妙なズレが関わっています。
それらを丁寧に読み取り、脳と身体の関係性を“つなぎ直す”ようなケアが求められるのです。
こうした領域は、一般的なマッサージやフィットネスとは明確に異なるアプローチが必要です。
第三の選択肢をあなたに
だからこそ私は、医療でも介護でもない、でも“医学的な視点と経験に裏付けられた第三の選択肢”を地域に届けたいと思いました。
実際、病院のリハビリでは限界があり、介護のリハビリでは物足りなさを感じる――そんな狭間で悩んでいる方が、松本・安曇野エリアにはたくさんいらっしゃいます。
**「もう一歩踏み出したい」「自分の身体と向き合い続けたい」**という想いを持つあなたが、安心して通える場所。
そんな場所を求めている方にこそ、必要なケアがあると私は信じています。
5. 「整体りびるど」でできること
キーワードは”感じ方のズレ”
整体りびるどでは、脳卒中後の片麻痺に対して、単なるリラクゼーションや筋力強化とは違う、**「神経と感覚と動きのつながりを整える」**という視点からアプローチを行っています。
私自身、長年脳神経外科病院で理学療法士としてリハビリに携わる中で感じてきたのは――
「回復を止めているのは、“動かし方”の問題ではなく、“感じ方”のズレ」であることが多いということです。
筋肉や関節の硬さよりも、“身体がうまく感じられていないこと”が、動きの滑らかさを妨げているケースが非常に多く見られました。
だからこそ、りびるどの施術ではまず「どんな感覚が抜けているのか」「どこで動きが止まっているのか」を丁寧に見極め、**“感覚の再入力”と“動作の再編集”**を行っていきます。
たとえば――
- 麻痺側の手足を「触れられている」と正確に感じられるようにすること
- 支持面(床や椅子)からの反力をきちんと受け取れるよう調整すること
- 関節や筋肉の動きが、神経の流れを邪魔せずに連動するよう整えること
これらはすべて、“元に戻す”のではなく、“思い出させる”ための働きかけです。
そして、施術だけで終わらせず、**「日常でどんな姿勢や動作を心がけるべきか」「どうすれば自分で整えられるか」**というセルフケアの視点もセットでお伝えしています。
それが、“受け身”ではなく“主体的に身体と向き合う”ことにつながるからです。
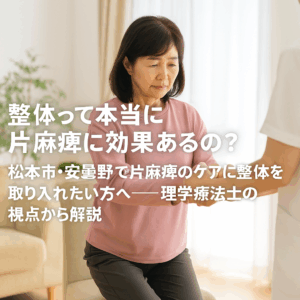
奇跡の魔法は存在しないけど
藁にもすがる思いでネットを探すと、魔法のように麻痺が良くなる、と言った類の宣伝文句を目にすることもあります。
しかしながら、私はそんな方法は「存在しない」と思っています。
脳卒中後の片麻痺の回復は、決して“特別な方法”が必要なのではありません。
大切なのは、正しい順序で、正しい感覚をもう一度身体に思い出させること。
そして、そのためには医学的な視点と繊細な感覚の読み取りが必要不可欠です。
松本市にある「整体りびるど」では、経験豊富な理学療法士がその両方を持ち合わせた施術で、あなたの「まだ動きたい」に丁寧に寄り添います。
6. 回復をあきらめない人に必要な“新しい視点”
正しい感覚と順序
私がこれまで脳卒中後の片麻痺の方々と向き合ってきて、強く感じていることがあります。
それは――「回復とは、努力の量ではなく、“正しい感覚と順序”で再構築すること」だということです。
医療の現場では、「筋力」「可動域」「麻痺の程度」といった“見える数値”が中心に評価されることが多くあります。もちろん、それらも重要な指標です。
しかし本当に動きが変わる瞬間というのは、本人の中で“何かに気づいたとき”に訪れるのです。
たとえば、「あ、今、麻痺側の足でちゃんと床を踏めてる気がする」
「なんだか今日、手の感覚がいつもと違う」
そんな“わずかな違和感”や“感覚の気づき”こそが、回復の入口だと私は考えています。
きっかけは気づきから生まれる
これは、“治す”という発想とは少し異なります。
私が目指しているのは、「戻す」こと。
身体が本来持っていた感覚や機能を、忘れていた記憶のように少しずつ思い出していく――そんなプロセスを一緒に辿ることなのです。
この考え方は、世界保健機関(WHO)が提唱しているICF(国際生活機能分類)の視点にも通じます。
ICFでは、障害を「能力の欠如」ではなく「環境との関係性で生じるもの」と捉え、“できる活動”や“参加”を広げていくことが重視されています。
つまり、本人の力を最大限に引き出しながら、“自分らしい生活”を取り戻していくという考え方です。
あなたの希望を再構築するために
片麻痺になったからといって、すべてを諦める必要はありません。
少しずつ整えていく中で、“もう一度歩いてみたい”“両手で作業をしてみたい”という気持ちが芽生えてくるなら――それは回復の力が、まだあなたの中に残っている証拠です。
私はその力を、ていねいに引き出すお手伝いをしたい。
ただの施術者ではなく、あなたの“再構築”を支える伴走者でありたい。
それが、整体りびるどの考える“本当のケア”のあり方です。
7. リハビリが終わった今こそ、“本当の回復”が始まる
本当の旅の始まり
リハビリが終わった――
それは、医療制度の中での“一区切り”かもしれません。
けれど、それは決して、あなたの身体の物語が終わったことを意味しません。
むしろ私はこう考えます。
「ここからが、“自分で自分を取り戻す旅”の始まりなのだ」と。
脳卒中後の片麻痺は、たしかに厳しい現実を突きつけます。
けれど、それでも人は、少しずつ順応し、少しずつ工夫しながら前に進む力を持っています。
その力は、努力や根性といったものとは少し違う、“自分の身体にもう一度ちゃんと耳を澄ます力”のようなものです。
「前よりはできなくなった」ではなく、
「今の身体でできることに、どう向き合っていくか」
その視点さえ持てれば、回復の道は細くても、確かに未来へとつながっています。
隙間を埋める方法はきっとある
もし今、「このまま終わっていくのは嫌だ」と感じているのなら――
それは、あなたの中にまだ回復する力が生きている証拠です。
私は、そんな想いを持った人とこそ、一緒に歩いていきたいと思っています。
医療でも介護でも埋められなかった“その隙間”を、
あなたの想いと、私の専門性とで、一緒に埋めていけたなら。
それは、きっと“再構築”と呼ぶにふさわしい時間になるはずです。
今回の記事は以上となります。
この記事が、いま悩みを抱えているどなたかの心に、小さな希望の灯をともすきっかけになれば嬉しいです。
大丈夫。私があなたに寄り添います。
まずはお気軽にご相談ください。現在のお身体の状態、お悩み、などどんなことでも構いません。
きっとあなたの、力になってみせます。
参考・引用文献
※1
Verheyden G et al. (2008). Trunk performance after stroke: an eye catching predictor of functional outcome. Stroke, 38(3):1310–1315.
※2
Nudo RJ. (2006). Mechanisms for recovery of motor function following cortical damage. Curr Opin Neurobiol, 16(6):638–644.
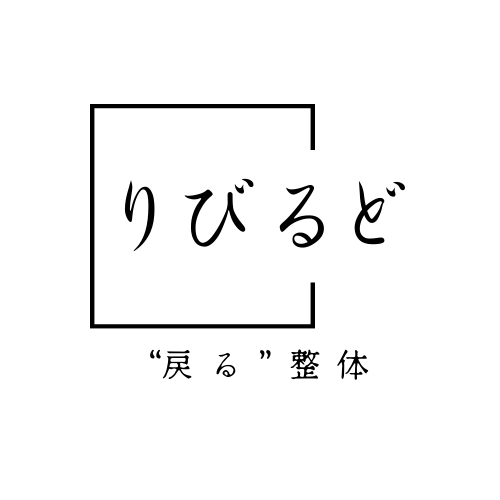
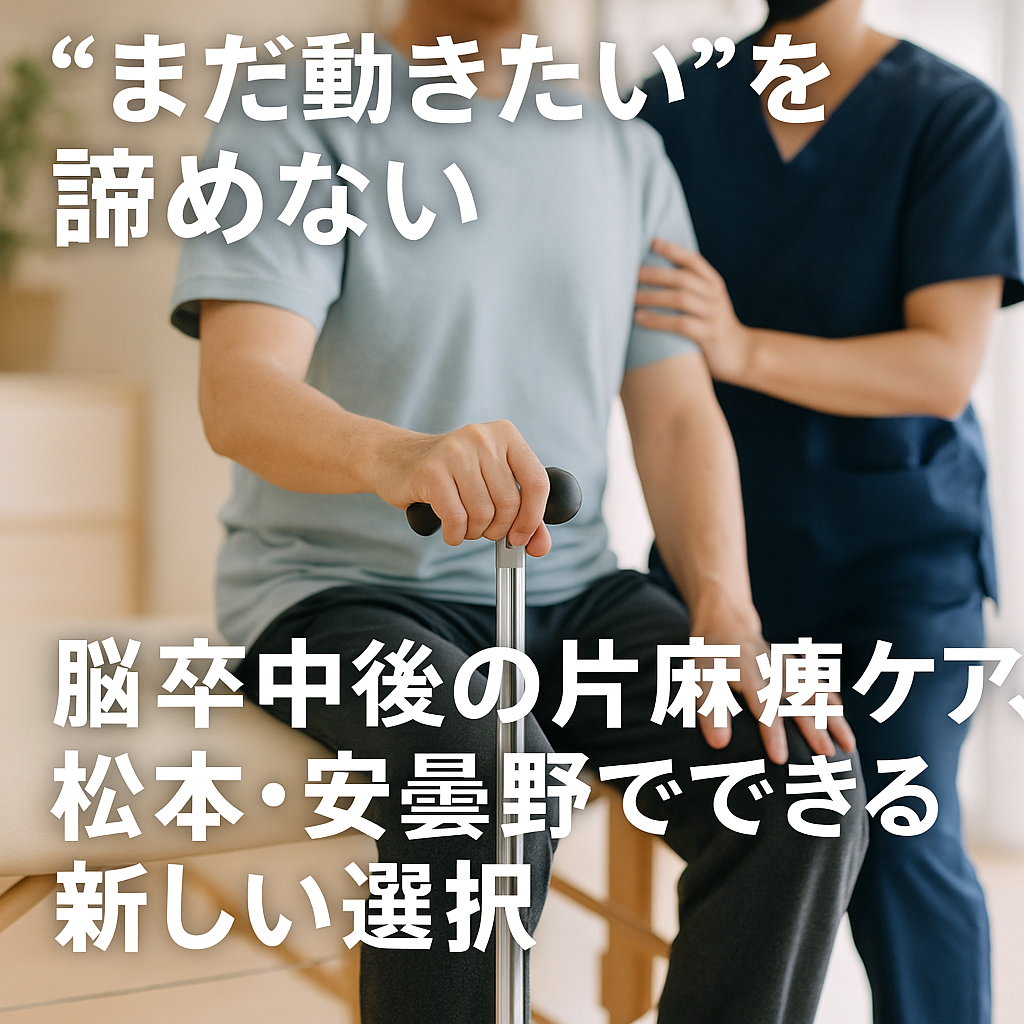




コメント