「病院でのリハビリは終わったけれど、まだ身体に不安がある」
「次はどこで、どんなリハビリを受ければいいのか分からない」
松本市・安曇野エリアでも、こうした声を多く耳にするようになりました。
実は、“医療のリハビリ”と“介護のリハビリ”は、目的も制度もまったく異なるものです。
そしてその違いを知ることが、「リハビリの空白期間」をつくらないための第一歩にもなります。
本記事では、医療・介護の両現場で経験を積んできた理学療法士の立場から、
医療と介護それぞれのリハビリの違いや、病院から在宅へとスムーズにつなぐためのヒントをわかりやすく解説していきます。
「リハビリを継続したいけれど、どう動けばいいのかわからない」
そんな方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。
最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。

医療のリハビリとは?──「回復」を支援するための期間限定ケア
病院でのリハビリは“治療の一環”
医療機関で提供されるリハビリは、基本的に「病気やけがからの回復を目的とした治療行為」です。
そのため、医師の診断のもと、理学療法士や作業療法士などの専門職が関わり、保険診療としてリハビリが実施されます。
たとえば、脳卒中で手足が動かしにくくなった方や、骨折後に日常生活が困難になった方に対して、「座る」「立つ」「歩く」といった動作の再獲得を目指して訓練が行われるのが典型です。
期限付きの制度に注意
ただし、医療保険でのリハビリには「期限」があります。
厚労省の制度では、たとえば以下のような上限が設けられています。
- 脳血管疾患(脳卒中など)…発症から最大180日
- 運動器疾患(骨折・変形性関節症など)…発症から最大150日
- 呼吸器疾患や心疾患など…それぞれに規定あり
この期限を過ぎると、たとえ本人が「もっと続けたい」と希望しても、医療機関でのリハビリは終了となってしまうことが多いのが実情です。
医療リハビリの“限界”は制度的なものである
ここで大事なのは、「期限が来たからもう回復の余地がない」というわけではないということ。
多くの方が、ようやく動き方に慣れてきたタイミングで制度的なリハビリ終了を迎えます。
この制度上の制限を理解したうえで、「その後にどう備えるか」が、次章以降のテーマにつながっていきます。
介護のリハビリとは?──「維持・予防」を目的とした生活支援型ケア

医療と目的が違う「介護リハビリ」
医療のリハビリが「治療」としての役割を持っていたのに対し、介護のリハビリは“生活の維持や予防”が主な目的です。
これは、介護保険制度の枠組みに基づいて提供されるリハビリであり、回復よりも“その人らしい暮らし”を支えることを重視しています。
たとえば――
- 買い物に出かけるための歩行練習
- トイレ動作や入浴動作の反復練習
- 家事動作や趣味活動へのアプローチ
こういった「日常の自立支援」を軸に、リハビリが行われます。
サービスの種類もさまざま
介護のリハビリには、以下のような形態があります:
- 通所リハビリ(デイケア):施設に通って行うリハビリ
- 訪問リハビリ:理学療法士などが自宅に訪問し、在宅環境に応じた指導を行う
- 施設入所リハビリ:老健や特養などに入所して継続的にケアを受ける
これらは、要介護認定を受けることで利用可能となります。
また、利用頻度や時間も「ケアプラン」によって調整されるため、医療リハビリのような“毎日の集中訓練”とは少し性質が異なります。
たとえば、70代のAさん(松本市在住)は、変形性膝関節症の手術後に病院でのリハビリを受けていましたが、退院後もしばらくは歩くのが不安で、外出も控えがちに。
主治医の勧めで、週2回のデイケアでのリハビリを利用することになり、膝への負担をかけすぎない運動や、歩行時のサポート具の使い方を練習。
「少しずつまた出かける気持ちになれてきた」と語ってくださっています。
このように、医療リハの“あと”に介護リハを上手く活用することで、身体だけでなく生活全体の質を高めていくことができるのです。
「もう治療は終わった」から始まる、もう一つのリハビリ
介護のリハビリは、「治すため」ではなく「できるだけ自立した生活を続けるため」にあります。
医療の現場でリハビリを経験した方が、その先も動ける身体を維持するために必要なケアとして位置づけると理解しやすいかもしれません。
つまり、医療から介護への移行は、“終わり”ではなく“次のステップ”。
この考え方が、次章で解説する「リハビリのつなぎ方」において非常に重要な視点となります。
介護保険で受けられるリハビリの特徴と注意点
“生活の中での自立”を支えるリハビリ
介護保険で提供されるリハビリは、「機能を回復させる」ことよりも、「その人らしく生活を送る」ための支援が主な目的です。たとえば、デイサービスや訪問リハビリなどを通して、日常生活の中で困っている動作(立ち上がり・トイレ動作・外出時の歩行など)に対してアプローチを行います。
こうした支援は、“訓練”というより“生活のサポート”に近い形で行われるため、医療リハビリと比べると、頻度や密度はどうしても控えめになる傾向があります。
担当は“医師”ではなく“ケアマネージャー”
もう一つ大きな違いは、「リハビリを必要とする」と判断するのが、医師ではなくケアマネージャー(介護支援専門員)であることです。医療では医師の指示のもとにリハビリが進みますが、介護保険下ではケアマネージャーが全体の支援プラン(ケアプラン)を立てるため、医療的な視点よりも“生活上の困りごと”が優先されることもあります。
そのため、たとえ身体的にはもっと積極的な訓練が必要だとしても、「介護サービスでは対応が難しい」となるケースもあるのが現実です。
“現場との対話”がリハビリの質を左右する
介護リハビリの質は、現場(デイサービスや訪問リハなど)との連携によって大きく左右されます。提供者によってリハビリの内容や姿勢に差があるため、「ただ通っているだけ」にならないよう、利用者やご家族が積極的に要望や目的を伝えることが大切です。
実際に、「目標が曖昧なまま1年経った」「本当は屋外歩行の練習がしたいのにできていない」といった声もあります。リハビリを“受ける側”が自分の希望を明確に伝えることも、効果的な介護リハビリの第一歩となります。
医療と介護、リハビリをつなぐための“空白期間対策”
「退院後の空白」が生まれる理由
退院後すぐに介護保険のリハビリにつながる方ばかりではありません。
実際には、
- 介護保険の申請に時間がかかる
- ケアマネジャーの選定・調整に時間がかかる
- 通所・訪問リハビリの空きがない
といった理由で、退院から実際の介護サービス開始までに「2〜4週間の空白」ができてしまうケースも少なくありません。
この期間中、十分な身体のケアがされないまま生活を送ることで、筋力や体力が落ちてしまったり、再び痛みや動作の不自由さが出てきたりすることもあります。
大切なのは「退院前」の準備と情報共有
こうした空白を防ぐには、「退院前」から次のステップを具体的に考え、関係者間で情報共有しておくことが非常に重要です。
- 医師やリハビリスタッフから、今後の身体の課題や注意点を確認する
- 必要であれば、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に早めに相談する
- ケアマネジャーが決まったら、退院前カンファレンスなどでスムーズに引き継ぎを行う
これらの事前準備が、リハビリの“中断”を防ぎ、継続的なサポートにつながります。
“つなぎの選択肢”としての自費リハビリ・整体
保険制度に頼らない「自費リハビリ」や「自費の整体」も、空白期間を埋める手段として注目されています。
特に、
- 退院後すぐにでも身体を整えたい
- 自宅でできるセルフケアの指導がほしい
- 医療でも介護でもない自由な視点で身体を見てほしい
といったニーズに対して、自費での施術や運動指導は柔軟に応じやすく、制度のはざまで困っている方にとって有効な選択肢となります。
もちろん、保険外であるぶん費用はかかりますが、「今、何もしないことで後々もっと困る」可能性を考えると、必要に応じて活用を検討する価値は十分にあります。
リハビリを“続ける”ことで、暮らしの質を守る
「良くなること」だけがリハビリではない
多くの方が、リハビリ=「良くなるためのもの」と考えがちです。
もちろん、それは間違いではありません。
でも実際の現場では、「現状を維持する」「悪化を防ぐ」こともリハビリの大切な役割だと、私は何度も実感してきました。
たとえば、退院直後は自立して歩けていたのに、リハビリをやめてしまったことで筋力が低下し、杖や介助が必要になる――。
そんなケースも現実には少なくありません。
「現状を保つこと」は、決して後ろ向きなことではなく、“今の暮らしを守る”という前向きな選択です。
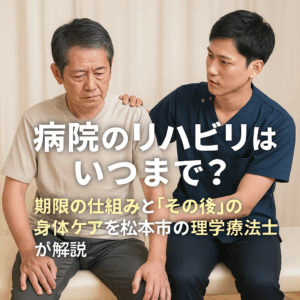
リハビリは“手段”であり“目的”ではない
リハビリは、それ自体がゴールではありません。
本来は、「自分らしく暮らすため」の手段にすぎないのです。
歩くこと、手を動かすこと、体を起こすこと――
そのどれもが、「日常生活を送るための手段」であり、「家族と過ごす時間を大切にしたい」「趣味を続けたい」「旅行に行きたい」といった“生活の質”を支えるものです。
その視点を忘れずにいれば、「期限が切れたからもう終わり」ではなく、「これからも続けよう」という気持ちになれるはずです。
“自分のための選択”をすることが、人生を整える
医療でも介護でも、その制度の枠を超えて、「自分には何が必要か?」を考えることが、これからのリハビリには求められています。
もし迷ったら――
ぜひ専門家に相談してみてください。
病院を出たあとも、あなたの身体を一緒に考えてくれる人はきっといます。
そして、自分に合ったリハビリを、自分の意志で選び、続けていくこと。
それこそが、これからの時代の「身体を整える」ということなのだと思います。
もしご自身やご家族のリハビリ継続について「次はどこに相談すればいいの?」と迷われたら、まずはお住まいの地域包括支援センターや担当ケアマネジャーにご相談ください。
状況に応じて、デイケアや訪問リハビリ、地域リハビリテーション活動などの支援策を一緒に考えてくれます。
もちろん、整体りびるどでも「医療と介護の間」で不安を感じている方のご相談をお受けしています。お気軽にご連絡ください。
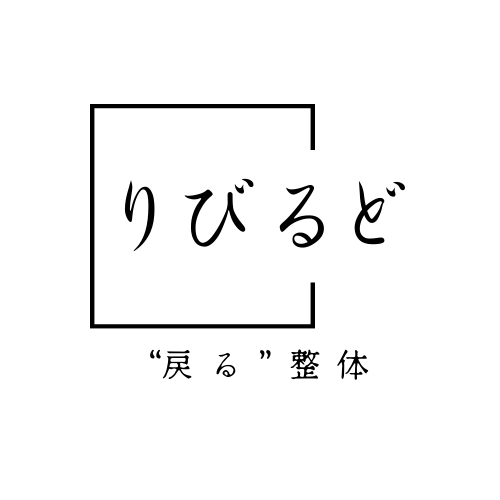


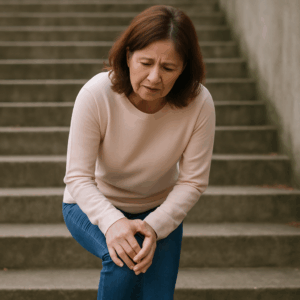




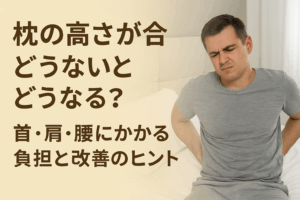

コメント