1. 肩こりは「姿勢の型」より「感覚のクセ」で決まる
肩こりの原因としてよく言われるのが「姿勢が悪いから」。
でも本当は、**“見た目の型”ではなく、“自分がどう感じてその姿勢を取っているか”**が重要です。
つまり――
- 背中が丸まっていても、ラクに感じている
- 肩に力が入っていることに無自覚
- 「いい姿勢を頑張って取っている」つもりが実は過緊張
このように、感覚のズレこそが肩こりを慢性化させる根本要因になるのです。
本記事では、そんな“肩こりを生みやすい姿勢パターン”を3つ紹介し、整え方のヒントまで掘り下げていきます。
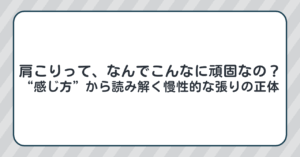
2. パターン①:骨盤後傾+背中丸まり型
【こんな人に多い】
- デスクワークやスマホ時間が長い
- 椅子の背もたれに寄りかかるのが習慣
- 腹筋が弱く、猫背がクセになっている
【特徴】
- 骨盤が後ろに倒れている(後傾)
- 腰が丸まり、背中が後方へ流れている
- 頭が前に出て、顎が上がっている
- 肩甲骨が外側に流れ、“浮いた”状態
【身体への影響】
- 首や肩の筋肉が常に頭を支える状態に
- 背骨のS字カーブが失われ、負荷が分散できない
- 肩甲骨の安定感が低下し、腕の動きにも影響
→ 首肩の過緊張・浅い呼吸・眼精疲労などが起こりやすくなります。
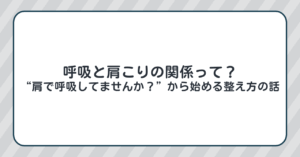
3. パターン②:反り腰+肋骨前突型
【こんな人に多い】
- 「姿勢をよくしよう」と意識しすぎる
- 腰を反って胸を張るのが“いい姿勢”だと思っている
- 呼吸が浅い・肩に力が入りやすい
【特徴】
- 骨盤が前に傾き、腰が反っている(前傾)
- 肋骨が前方に突き出し、胸を張りすぎている
- 肩が後ろに引かれ、腕が不自然に後ろに位置している
【身体への影響】
- 首や腰に反りストレスがかかり、緊張が高まる
- 肋骨が硬くなり、呼吸が“浅く速く”なる
- “いい姿勢”を頑張りすぎて、脱力できない
→ 緊張型肩こり・慢性疲労・頭痛・腹圧の低下に繋がることも。
4. パターン③:片重心+左右差固定型
【こんな人に多い】
- いつも同じ足で立つ・荷物を同じ肩で持つ
- 座るときに足を組む癖がある
- 肩の高さや骨盤の位置に左右差があると感じる
【特徴】
- 立位・座位ともに片側に体重をかけやすい
- 背骨がS字ではなく“くの字”になりやすい
- 肩や骨盤に高さの違いがある
【身体への影響】
- 片側の肩甲骨周囲の筋緊張が高まる
- 逆側は感覚が鈍くなり、補正が効かなくなる
- 肋骨の動きや呼吸の偏りも生じやすい
→ 肩こりが“片側だけ”に出る方は、このタイプであることが多いです。
5. 姿勢を整えるには“まず気づくこと”から
これら3パターンの共通点は、**“感覚の偏り”**です。
- 背中が丸まっていることに気づいていない
- 腰が反っているのに“よい姿勢”と信じている
- 重心が偏っているのに“真ん中にいる”感覚になっている
つまり、「整える」の第一歩は、自分の“ズレ”に気づくこと。
そしてそれは、鏡で確認するのではなく、“感じる力”を再構築することによってはじまります。
6. すぐにできる感覚リセットのヒント
「じゃあ、どうやってズレに気づけばいいの?」
そんな方におすすめの、簡単な“姿勢センサーリセット”ワークを3つご紹介します。
✔ 足裏3点支持チェック
母趾球・小趾球・かかと、3点に均等に立てているか?
→ 重心のズレに自然と気づくことができます。
✔ 背中と壁の接触チェック
壁にかかと・お尻・背中・後頭部をつけて立ち、
→ 背中や頭の“浮き”を感じることで、自分の姿勢にフィードバックが得られます。
✔ 椅子で坐骨を感じて座る
イスに座るとき、“お尻の骨(坐骨)”で座れているか?
→ 骨盤の位置が整い、上半身の力が抜けやすくなります。
これらはどれも1〜2分でできる**“身体の感覚を取り戻すスイッチ”**です。
7. “正す”より“つながり直す”整え方を
肩こりの原因は“姿勢の崩れ”と言われますが、
実際には**“身体とのつながりが薄れていること”**の方が重要です。
だからこそ――
- 見た目を直すのではなく、感覚を取り戻す
- 力で抑えるのではなく、支えを感じる
- 部分だけでなく、全体の連動で整える
そんな視点で身体を見直していくと、自然と姿勢が変わり、肩こりは“ラクな状態”に向かっていきます。
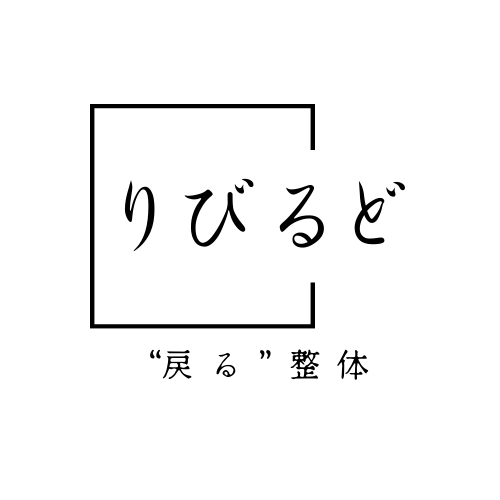
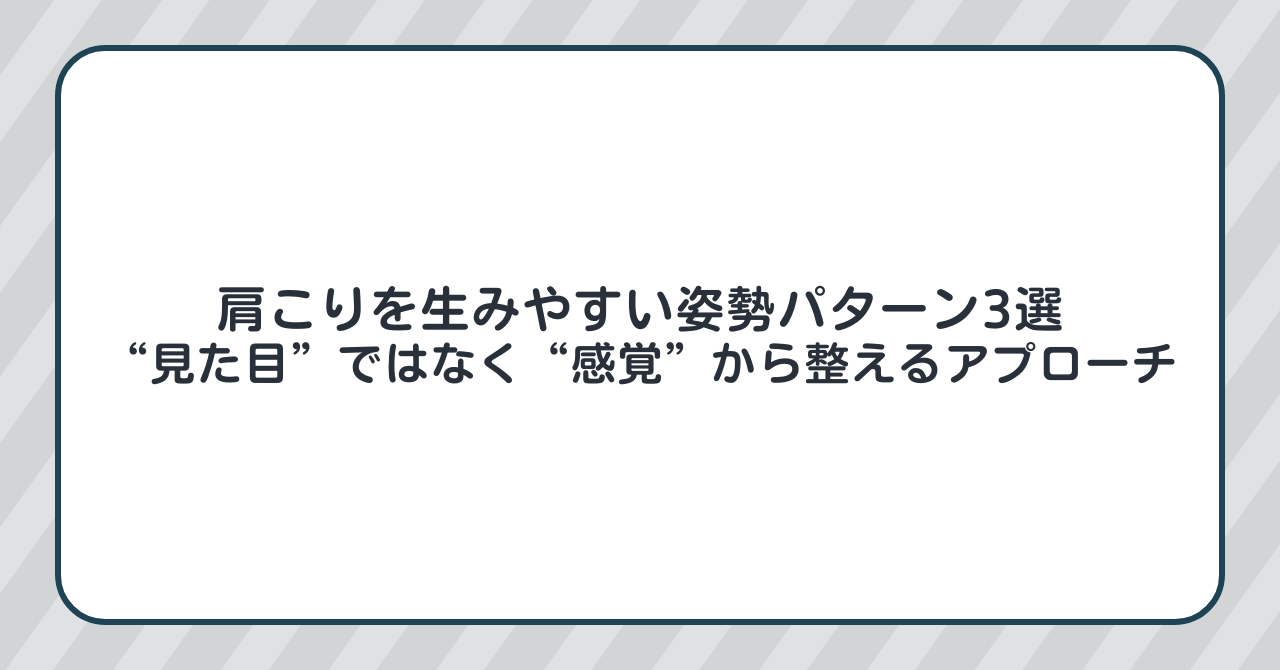


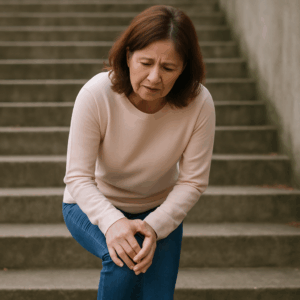




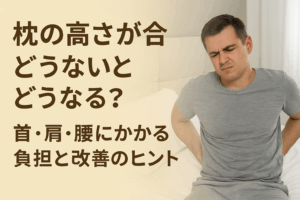
コメント